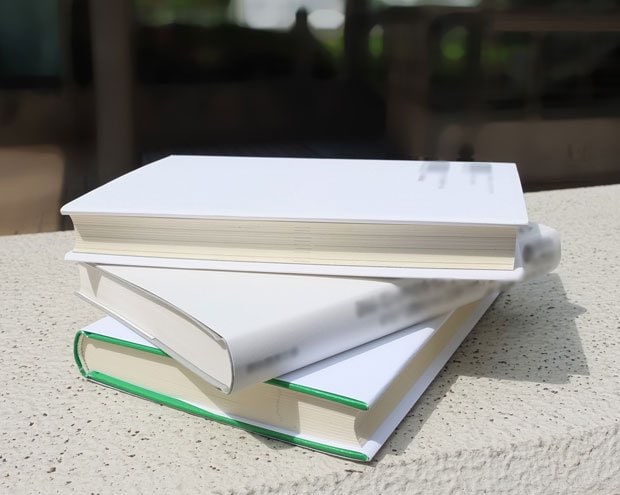
夏休みは受験生にとっては「夏を制す者が、受験を制す」とも言われる大事な時期。今のうちに苦手を克服しておきたいところ。『脳を一番効率よく使う勉強法』などの著書がある、医学博士で受験アドバイザーの福井一成さんが、脳科学の面からその方法を紹介する。
そもそも、苦手というのは、脳科学的にはどういう状態なのか。福井さんが、こう解説する。
「点が取れないとその科目が嫌いになり、不快なときに出るノルアドレナリンという脳内ホルモンが分泌されます。ノルアドレナリンは、記憶をつかさどる海馬の働きをダウンさせるため、その科目の勉強が進まなくなり、点数が取れないという悪循環に陥るのです」
この反対に、勉強が楽しいと、「脳内モルヒネ」「幸せホルモン」などと呼ばれるβエンドルフィンが分泌され、海馬の記憶力がアップし、勉強がはかどる。その結果、成績が上がり、さらに勉強が楽しくなる。
「ウソでもいいから『勉強は楽しくて快感だ』と思い込むことです。βエンドルフィンが分泌され、本当に『勉強は快感』と感じられるようになります。すると脳内でさらにβエンドルフィンが分泌され、『勉強がもっともっと快感』になります。このとき、決してマイナス思考をしないことです。『勉強なんてつまらない』と思った瞬間、ノルアドレナリンが出て、いい循環を断ち切ってしまいます」
福井さんによると、ある科目が苦手になった原因は、その科目の勉強法が間違っているか、その勉強法の効率が悪い場合が多いという。
「苦手科目は、わかりやすくて解説が丁寧な参考書・問題集を使いましょう。必ず書店で手にとって解説を読む。そして自分に合ったものを選ぶことが大切です」
同じ問題集を、解けない問題がなくなるまで、何度も繰り返すことも必要だ。
福井さんは、脳科学的に正しい苦手克服法として、次の勉強法を勧める。
【1】音読勉強法……英単語、古文単語、公式などをなかなか覚えられない人は、「黙読」ではなく、「音読」すれば脳が活発に動き、暗記しやすくなる。耳栓をした状態で参考書の文章を指でなぞりながら、ささやき声で読むと、骨伝導で声が頭の中で大きく響くため、集中力がアップする。
【2】右脳記憶法……感性、感覚をつかさどるといわれる右脳の記憶容量は、論理的働きをするとされる左脳の記憶容量の10倍以上あるため、右脳を受験勉強に利用すると、早く覚えられる。地理・歴史・化学・生物などの勉強は、最初に「イラスト・絵・写真」を見て、そのイメージを右脳で暗記。それから「本文・語句」を左脳で暗記する。
【3】聴覚記憶法……【1】と【2】をミックスした勉強法。参考書を音読するときに、ICレコーダーに録音する。その音声を聞いて覚えるとき、左脳は「言語」として暗記するが、右脳は聞こえたままの「音」として暗記する。試験のときに左脳が答えの語句を思い出せなくても、右脳が覚えている音をきっかけに、左脳が語句を思い出せる。通学時や、疲れてベッドに寝転んでいるときにも聞くことができるため、時間の節約にもなる。
脳科学的手法を採り入れて、夏の果実を手に入れてほしい。
※週刊朝日 2015年8月7日号より抜粋








































