
BOOKSTAND


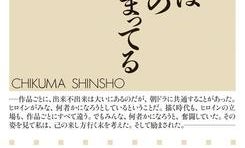
「朝ドラ」は働く女子のカンフル剤!? 女性を熱狂させる「朝ドラ」の魅力とは
古くは「おしん」、近年では「あまちゃん」など、数々の流行語や社会現象を世に送り出してきたNHK連続テレビ小説、通称「朝ドラ」。現在放映中の「半分、青い。」でも、永野芽郁さん演じるヒロインの出身地、岐阜県の郷土料理「五平餅」や土産品「さるぼぼ」、井川遥さん演じる登場人物が着用した「ピンクハウス」などがSNS上で話題になるなど、その影響力は見逃せません。本書『朝ドラには働く女子の本音が詰まってる』では、そんな朝ドラ人気の理由を読み解き紹介しています。 本書の中で特に言及されているのが、2011年放映の「カーネーション」。型破りなヒロインが洋裁に魅せられ起業する一生を描き、朝ドラ史上最高傑作の呼び声も高い作品ですが、著者の矢部万紀子さんは、同作における戦争描写を評価し、こんなシーンを取り上げています。 物語も終盤に差し掛かった頃、最愛の息子を戦争で失った母親が当時を振り返り、ヒロインに述懐します。同作の中ではそれまで、ヒロインの幼馴染だった息子が、戦地から帰還後に鬱状態になってしまった様子も描かれており、母親はずっと「息子は戦争に行って余程ひどい目に遭わされたのだろう」と思い込んでいたと語ります。しかし、戦後20年が経過したある日、母親は偶然にも、当時の日本軍の行為を知り、息子が心を病んでしまった本当の理由を悟ったと述べます。 「あの子は、やったんやな。あの子が、やったんや」(本書より) "ヘタレ"でお人好しな若者が、赤紙1枚で召集され、否応無しに"加害者"にされてしまったこと。戦時下においては好むと好まざるとに関わらず、誰しもが被害者側に成り得ると同時に、加害者側にも容易に成り得るという、戦争の残酷さを正面から描いたドラマだったのです。 戦後70年が過ぎ、当時に比べれば女性の地位も格段に向上した現代ですが、それでも社会や職場で、何らかの生きづらさを抱える女性も少なくないのではないでしょうか。朝ドラヒロインの奮闘ぶりから、働く女性なら誰しも共感できるエッセンスを抽出した本書を読み通せば、何かしらのヒントが見つけられるかもしれません。
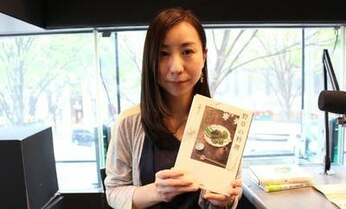
雑草の調理法が紹介された一冊『野草の料理』が印象深い------アノヒトの読書遍歴:コトリンゴさん(前編)
音楽家のコトリンゴさん。2006年3月、坂本龍一のラジオ番組J-WAVE「RADIO SAKAMOTO」宛にデモテープを送ったことがきっかけで、同年11月に「こんにちは またあした」でデビューを果たします。2017年11月には自身のレーベルkoniwaからアルバム『雨の箱庭』をリリース。今年5月には音楽フェス「Lotus music & book cafe'18」に出演し、6月23日には「Live 2018〜雨の雫とピチカート〜 with 徳澤青弦カルテット」を開催します。そんなコトリンゴさんは普段からさまざまな本を読むといい、今回はコトリンゴさんの日頃の読書生活についてお話を伺いました。
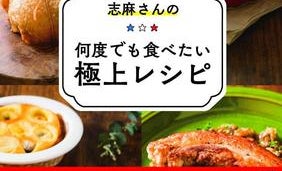
"伝説の家政婦"の家には調理器具が2つだけ?
「伝説の家政婦」としてテレビなどで話題の、家政婦の志麻さん。注目の理由は何といってもその料理の腕前で、あらゆる材料を無駄なく効率的に使い、わずか数時間で10品以上もの料理を仕上げる手際の良さは、圧巻。もちろん出来上がった料理はどれも美味しそうで、その上どこかオシャレ。その圧倒的なポテンシャルの高さで注目されています。 そんな話題の志麻さんですが、意外に知られていないのがその素顔やルーツ。実は志麻さんの料理には、彼女が料理の研修のために訪れた、フランスでの日々が大きく影響しているのです。本書『志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ』は、志麻さんお気に入りのフランス家庭料理のレシピをまとめた一冊。レシピの他にも、彼女が影響を受けたフランスの料理文化などについてのコラムも収められており、志麻さんのルーツも少しだけ垣間見ることができます。 大阪の調理師の専門学校で料理を学び、フランスのミシュラン三ツ星レストランで研修を受けた志麻さんは、その後、有名フランス料理店に料理人として15年間勤務。しかし、その間も忘れられなかったのがフランスで出合った家庭料理なのだそう。日本では「手がかかって高級」なイメージがあるフランス料理ですが、家庭料理はとてもシンプルでおいしく「食べるとしあわせな気分になるものばかり」と志麻さんは同書で語ります。また、現地ではフランス人の食への関心の強さや、意識の高さを感じたと言い、そのエピソードも紹介しています。 例えば、豪華なイメージのあるフランス料理ですが、実は食材を無駄にしない細かな工夫があると言います。トマト缶などを使う際は、ほんの少しでも無駄にしないように、中身を空けた缶に少量の水を注いで鍋に戻す。煮込み料理で、煮込む前に使ったフライパンに旨味が残っているようなら、余分な油をふき取った後に煮込みに使うワインを入れ、旨味をこそげ落として料理に使う。志麻さんは、こうした現在の自身につながるような、フランス料理の効率的で無駄のない調理法を厨房で学んだと語ります。 また、フランス人の食に対する意識の高さは、一般家庭の中にも垣間見ることができたと言います。フランスの子どもたちは大人と同じように自分で料理をお皿に取り分けて食べるのですが、もしお腹いっぱいで食べきれずに残してしまうと、親は厳しく叱るのだそう。それは、自分が食べられる分だけを自分のお皿に取り分けるのがマナーだから。「フランスの子どもたちは食事をしながら食育を受けているのだなと感じることがありました」と振り返っています。 さらにコラムからは、テレビではあまり映されることのない、志麻さんの素顔が垣間見える部分も。 実は志麻さん、フランス人の夫と結婚した当初、仕事やフランスの文化を学ぶのに忙しく、家には小さな鍋と大きなフライパンしか、調理器具がなかったのだとか。そんな中でも夫に美味しいものを食べてほしいと考えた志麻さんは、この2つをフル活用。すると、「この料理も! あの料理も!」と意外なほど何でも作れることが分かったのだそうです。「ずっとレストランの厨房の整った環境のなかでフランス料理を作っていた私でしたが、どこにでもある普通のキッチンで作る家庭料理こそ、私が求めていたものだったのです」と自身の思いを再発見したことを明かしています。 さらにフランスでは、フランス人が男女ともにキッチンに立つ姿や、週末になると家族や友人たちと集まり、何時間もかけて食事と会話を楽しむ様子などが印象的だったと言い、「そうやって、フランス人が食をライフスタイルの真ん中において生活していることをいろんな場面で見て、心の底から『いいな』と思ったことが今の仕事につながっている気がします」と、「伝説の家政婦」の根源が垣間見える一文も登場します。 志麻さんに影響を与えた、フランス家庭料理の魅力が詰まった同書。煮込み料理やオーブン料理、デザート、いつもの料理を"格上げ"してくれるソースのレシピなどが掲載されており、一つでも覚えれば料理の幅がぐっと広がるはず。シンプルなのに、いつもとは一味違って、なんだかオシャレ。そんな志麻さんの料理の"ルーツ"を感じさせてくれる一冊です。
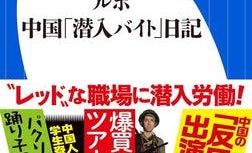
働き方、おかしいのは日本人? 中国で"潜入労働"した著者のトークイベントが開催
今日本でも話題の「働き方」ですが、働き方について大いに考えるトークイベントが、下北沢の本屋B&Bで行われます。 これは、今年3月に刊行された新書『ルポ 中国「潜入バイト」日記』(小学館新書)に絡めたイベントで、この本の著者で、実際に自身が中国人の働く現場に潜入&労働したライター・西谷格さんと、日本人の働き方を研究し、『社畜上等!』『なぜ残業はなくならないのか』などの著作がある評論家・常見陽平さんが登壇。日本と中国の働き方の違いや、働き方改革についてをテーマに激論を交わします。 「社畜」「ブラック企業」「サービス残業」など、現在の働き方改革をめぐる日本人の労働意識は一切ない中国人。もしかして、会社に忠誠を尽くす日本人のほうが、世界的に特殊なの......? 他国、他文化の働き方を紐解くことで、これまで普通だと思っていた働き方を新たな角度から客観的に分析することができるかもしれません。 アルコールを交えてトークを楽しめるこのイベント。気になった方は、詳細など本屋B&Bの公式サイトでチェックしてみてください。 ■本屋B&B http://bookandbeer.com/
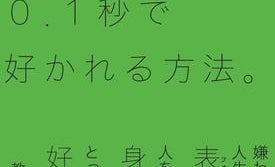
嫌われ続けの人生を克服した著者が教える「人を惹きつける方法」とは
私たちが日常でよく使う「空気を読む」という表現。人間関係をうまく築いたり仕事を円滑に進めたりする際に必要なスキルとして、皆さんも認識しているのではないでしょうか。 けれど、空気を読まずしてたった0.1秒で人を惹きつける方法が実はあるというんです。それを教えてくれるのが、本書『空気を読まずに0.1秒で好かれる方法』。著者の柳沼佐千子さんは今でこそ印象力アップトレーナーとして多くの企業で研修や講演をおこなっていますが、もともとは彼女自身が「嫌われ続けの人生」だったといいます。 子どものころから人前で話すことが大の苦手。学校ではイジメに遭い、社会人になってからは事務職、司会業、ラジオ局のパーソナリティ、ケーブルテレビのアナウンサーなどさまざまな職業を経験したものの、どの職場でも人とうまくいかない現実に直面してきたのだとか。 強烈なエピソードとしてはこんなものも。新しい美容院に行き始めて1年半ほど経ったときに担当の美容師さんから「柳沼さんが初めてうちの店に来たときのこと、今でもよく覚えていますよ。実は、ドアを開けて入ってきた瞬間、『うわ、この人誰が担当するんだよ。まさかオレ?』って心の中で思っていたんですよ」と言われたこともあるといいます。 こうした第一印象について柳沼さんは「ピンクのスイッチ(サングラス)」と「黒のスイッチ(サングラス)」にたとえて説明しています。最初の印象が良いと、その時点で人はピンクのスイッチが入り、心の目にはピンクのサングラスがかかり、相手のあらゆる言動が良く見えたり信頼がおけると感じたりする。逆に、最初の印象が悪いと黒のスイッチが入り、黒のサングラスがかけられて、相手のあらゆる言動が気に入らなくなったり、疑いの目を持ったりするのだと......。 厄介なのは、自分ではどちらの色のサングラスをかけているか気づかないこと。そのため、自分では相手のことを第一印象だけで決めた先入観ありきの判断をしているという認識がないこと。そして初対面で一度かけてしまったサングラスは、相手に変化がない限り、2回目、3回目に会ったときも自動的にかけてしまうものだということです。 こう考えると、第一印象で「この人、好きだな」「好感を持てるな」と思ってもらうことがどれほど大切か皆さんもわかってくることでしょう。 「人に好かれるために空気を読む必要はない」にくわえてもう一つ、柳沼さんのメソッドで驚くのが「正しく話せなくても大丈夫」というもの。しゃべりの技術の中でもっとも重要な要素は「声」だという柳沼さん。なぜなら人は話す内容ではなく、見た目や声の様子を頼りに内容を判断するからだというのが彼女の考え方。そのためにはどのような声の出し方や伝え方をすればよいかなども本書では具体的に書かれています。 本当の自分を隠してまで場の空気を読むことを優先するのではなく、仕事であってもプライベートであってもそのままの自分で好かれる生き方をすることが本書の目指す姿なのだとか。そこには、「なんとなく感じが悪い」という理由で嫌われ続けてきた中で、自らを実験台に実践して追求し、「好かれるフォーム」を確立した柳沼さんならではの思いが感じられます。空気を読むことに疲れた人、なぜか人に悪い印象を持たれやすい人、人間関係をうまく築きたい人......そうした人は本書を一読して、ぜひ実践してみることをオススメします。

デンマークの人々が幸せなのはなぜ? 「ヒュッゲ」に学ぶ暮らしのヒント
2012年にスタートした国際連合の幸福度調査において、2017年までの過去3回首位に輝いているデンマーク。2017年の発表では150以上の国や地域の中で日本が51位だったということを知れば、デンマークの国民が日頃どれほど幸福度や満足度を実感しているか、少し想像できるかもしれません。 そんな「世界一幸せな国」とも言われるデンマークにおいて、独特の文化として存在するのが「ヒュッゲ」。 「ヒュッゲ」とはデンマーク語で、「幸福」や「心地よさ」を表す言葉。本書『世界一幸せな国、北欧デンマークのシンプルで豊かな暮らし』の著者である芳子ビューエルさんは「大切な家族や親しい友人知人とともにほっこりした時間を過ごす」といった意味合いで解釈しているといいます。 国民の幸福度が高いいっぽうで、自殺率が高く、うつ病患者が多いという側面も持っているデンマーク。秋から春までの日照時間が非常に短いこの国では、暗く寒い日々が続くことから憂うつな気持ちを感じたり無気力になったりするのも無理はないことなのかもしれません。 だからこそそこで大事になるのがヒュッゲの考え方。「自分たちの『巣』を少しでも温かく、楽しく、心地よいものにして、自分が孤独ではないことを実感するためにヒュッゲという概念を生み出してきたように思えてなりません」と芳子さんは本の中で分析しています。そして、この最高に居心地のいいライフスタイル"ヒュッゲ"を私たち日本人にも提唱したい。その思いをもとに、北欧流ワークライフデザイナーである彼女が書きおろしたのが本書なのです。 この本では家具やインテリア、自然、エコなどさまざまな観点からヒュッゲが紹介されていますが、頻繁に登場するのがタイトルにもある「シンプル」とうワード。もくじには「幸せの背景には『シンプル』がありました」「わが家ではじめたシンプルなデンマーク流」「コペンハーゲンの住まいは、いたってシンプル」「シンプルでナチュラル--温かなホーム・パーティ」「すっきり片づいたシンプルな室内は北欧バイキングの遺産!?」といった見出しが並んでおり、ヒュッゲの概念にいかにシンプルさが大事となるのかが感じ取れます。 そのための実例や考え方などがきちんと書かれているのも本書の強み。たとえば「収納家具を置くのであればできるだけ背の低いものに」「窓のサイズを無視してカーテンをかけてみる」「マイチェアを置いて自分だけの空間をつくる」「とにかく戸外に出て陽に当たる」など家が狭くても、お金をあまりかけなくてもできる工夫がいろいろと載っています。これは北欧輸入の第一人者として何度もデンマークを訪れ、現地の人々とも親交の深い著者だからこそ提案できることといえるでしょう。 「ヒュッゲ」は日本の「おもてなし」に通じるところもあるという芳子さんですが、他にも日本とデンマークには不思議と共通点が多いのだとか。「自然や人間関係を大切にする」「豪華絢爛なものよりも質素でつつましやかな美しさを愛する」といった価値観や美意識から、住まいがけっして広いわけではないといった住環境にいたるまでいろいろと似通っているそうで、そう考えるとヒュッゲも実は私たち日本人が受け入れやすいものだと考えられます。 最近、日本でも根付いてきた「ミニマム」という考え方。物にあふれた現代社会で物に囲まれずに暮らすなんてむずかしいと思う人も多いでしょう。けれど、実際に「暗い、寒い、少ない」国に住んでいるデンマークの人々が自分たちをとても幸せに感じているということは、幸福というものは考え方次第、方法次第なのかもしれません。 身の回りのものはもっと少なくシンプルに、けれど今よりももっと幸福感や満足感のある毎日を送りたい。「ヒュッゲ」の概念はきっと、それを叶える鍵となってくれるのではないでしょうか。
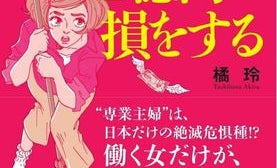
今の日本、働く女だけがお金も恋愛も自由も手に入れられる......!?
2016年のある調査では、若い女性のうち10人に3人が「将来なりたい」と答えたという"専業主婦"。「あこがれる」「つまらなそう」と人によってイメージはさまざまかと思いますが、「専業主婦は2億円をドブに捨てているようなもの」であり「専業主婦にはなにひとついいことがない」という主張をしているのが本書『専業主婦は2億円損をする』です。 なぜ2億円も損をするのかというと、筆者の橘 玲さんによるとこれはとても単純な話。大学を出た女性が60歳まで働いたとして、平均的な収入の合計は2億1800万円だからだそう(退職金は含まず)。結婚や出産で退職して専業主婦になった人は、40年かけて2億円になる「お金持ちチケット」を捨ててしまうことになるのだと橘さんは説明しています。 金銭的な話だけではなく、精神的な部分でも橘さんは専業主婦になることを薦めてはいません。プロローグでは「専業主婦は自由がない」「専業主婦は自己実現できない」「専業主婦の子育ては報われない」「専業主婦は最貧困のリスクが高い」「専業主婦になりたい女子は賢い男子に選ばれない」などデメリットが並びます。なかなか過激な物言いであり、これはともすれば炎上しかねなそう......。 けれど、本書を読み進めて行けば、筆者の考えに賛同できる人も多いことでしょう。筆者は海外との比較や調査データなども出しながら、たいへん具体的になぜ専業主婦にはなにひとついいことがないのかが述べられています。 たとえば、先進国の中では8割の女性がずっと働き続けるものの、日本だけが出産・育児を機とする25歳から30代にかけて就業率が落ち、そうして子どもに手がかからなくなった40代からまた上昇を始めるのだそう。今では大企業では女性社員が産後も働き続けられる制度を用意していますが、それは「マミートラック」と呼ばれ、第一線で働く社員とはちがう「ママ向け」仕事である場合も。また、いったん子育てに専念し再度働く場合は正社員ではなくパートやアルバイトとして働く女性も多いものです。 日本では子どもを産んだとたんに女性を取り巻く環境が大きく変わり、一見男女平等に見えても「女性が子どもを産むと"差別を実感する社会"」であることは、多くの女性が感じていることではないでしょうか。 さらに、筆者は専業主婦として夫に生活のすべてを依存している点にも疑問を投げかけます。「幸福とは自由(自己決定権)のことであり、そのためには経済的に独立していなければならない」「ほんとうの愛情や信頼は対等な関係からしか生まれない」という考え方もまた、男女問わず、独身既婚問わず、うなずけるところなのではないでしょうか。 とはいえ、現在の日本の社会で女性が産後も働き続けるというのは本当に大変なことです。「現在の非婚化や少子化というのは、日本の社会が『結婚して子どもを産んでもロクなことがない』という強烈なメッセージを、若い女性に送っているということ」と筆者は書いていますが、まさにその通りでしょう。ずっとシングル、あるいは好きな男性と一緒に暮らすけど結婚はしないという「ソロリッチ」が日本の社会で幸福になる有力な人生戦略であることは間違いないとはいえそうです。 けれど、そこにたったひとつ足りないものがあります。それは「子ども」。「やっぱり子どもも欲しいし働き続けたい」と思うなら、それには別の新たな戦略が必要となってきます。 筆者は本書でいくつかの戦略を紹介していますが、もっとも強く薦めているのが「会社で働かなくていいという戦略(フリーエージェント戦略)」です。フリーエージェントとは「好きなこと」に人的資源のすべてを投資するクリエイティブな「ソロリッチ」であり、ソロリッチ同士がカップルになって「ニューリッチ」となることがこれからのカッコいいライフスタイルなのだと提案しています。アメリカではニューリッチのライフスタイルは「BOBOS(ボボズ。ブルジョアとボヘミアンを組み合わせた造語)」と呼ばれ、"リベラルでカジュアルなお金持ち"といった意味合いでとらえられているのだとか。 フリーエージェントとなり年収800万円ずつ稼ぎ、夫婦で世帯収入1500万円を目指すニューリッチとなる。たしかにこれは今の日本で理想のライフスタイルであるに違いありません。本書は今の閉塞的な社会から抜け出るためのライフスタイルや働き方を提案し、女性が自由を手にするための一冊になっているといえるかもしれません。
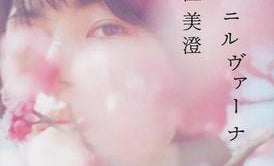
いつか誰かと居たことを懐かしむ前に、差し込む光のように
かつて新人類と呼ばれた世代に「少年A」よりもずっと前に幼女を数人殺害し、「おたく」という言葉に対してネガティブな印象を日本中にもたらした宮崎勤がいた。彼は数千本のビデオテープの孤独な籠城だけが拠り所だった。ある人が彼と同じ姓である宮崎駿の作品を観ていたら、宮崎勤はきっとあんな犯罪を犯さなかっただろうと言ったらしいが、その数千本のビデオテープの中でラベルに唯一「さん」づけされていたのがその監督だと昔何かで読んだことがある。宮崎勤だけではなく、「少年A」と同学年である九州バスジャックや秋葉原通り魔事件に、PC遠隔操作事件の犯人であるかつての少年たちは書きかけの小説やなんらかの表現をしていたと言われている。だが、それらは未完成だったりしたし何よりも他者には届かなかった。彼らが表現しようとしたものは一体なんだったのか? 何を見ようとしていたのか?


多いときには月に50冊くらい本を読む------アノヒトの読書遍歴:広瀬彩海さん(前編)
ハロー!プロジェクトの5人組アイドルグループ「こぶしファクトリー」のリーダー広瀬彩海さん。2011年、12歳のときにNICE GIRL プロジェクト!研修生としてアイドル活動をはじめました。2015年1月、現在所属している「こぶしファクトリー」の結成が発表されメンバーに加わり、同年3月にリーダーに就任。現在は音楽ライブやイベントなどを中心に活動を展開し、今年3月にはニューシングル『これからだ!/明日テンキになあれ』をリリースしました。そんな広瀬さんは普段から多く本を読むといい、今回は広瀬さんの日頃の読書生活についてお話を伺いました。

































