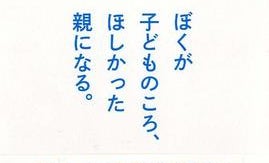
ガンで余命宣告を受けた35歳の父が、2歳の息子に伝えたい大切なこと
私たちが親になったときに誰もが思うこと。それは「子どものために自分は何ができるだろうか?」ということではないでしょうか。そして、もし自分の命がこの先長くないとわかっていたなら、限られた時間の中で何を残すことができるのかと、さらにその気持ちは強まることでしょう。 『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる』は、35歳にしてガン(多発性骨髄腫)で余命3年という宣告を受けた写真家・狩猟家の幡野広志さんが、2歳になった息子さんのために伝え残したいことを書いた一冊です。 ガンの宣告を受けてから、息子に残したいものは何だろうと考えたという幡野さん。それはお金などではなく「言葉」だということに気づきます。「息子自身の役に立つ言葉を残してあげたい。息子が成長していくうえでの、地図のような、コンパスのようなもの。いろいろと迷ったとき、『自分の父親だったらどう解決していたのかな?』と振り返ることができるものを残したいと思った」と記しています。 親であれば、子どもに伝えたいことなんて山ほどある。幡野さんは本書で「優しさについて、僕が息子に伝えたいこと」「孤独と友達について、息子に学んでほしいこと」「夢とお金について、息子に教えておきたいこと」「生と死について、いつか息子と話したいこと」という4つの章にわけて、自分の考えを伝えています。 中でも「優しさ」は幡野さんにとっては、第1章と最初のテーマに持ってくるほどとくに大切に感じているもののよう。優しい人が好きだから優しい人と結婚したという幡野さんは、息子さんにも「優」という名前をつけたといいます。そこには息子への願いが込められていると同時に、「僕たちは、優しい人になります」という幡野さんと奥さんが親になるための誓いでもあったのだとか。人に優しい人間になってもらいたいなら、まずは自分が人に優しくしなくてはいけない。当たり前のことでありながら、言われてみるとハッとさせられるものがありませんか? こうした幡野さんの優しい視点、まなざしはこの一冊を通して満ちあふれています。 このように、本書は「父親が自分の息子に宛てて書く」というとてもパーソナルな内容でありながら、それでいて誰にでも通じる普遍性も併せ持っています。幡野さんが息子に伝えたいこと、自身の状況についてなどブログに書き始め、取材なども受けるようになってから、ツイッターでは見知らぬ多くの人から悩み相談が届くようになったといいます。それに答えることで、息子さんが将来ぶつかる「困りごと」の手がかりが見つかるかもしれないと思い、息子さんに答えるつもりで正直に答えたと幡野さんは言います。そして逆に、「息子のための言葉が、悩みを抱える人にも役立ってくれたらうれしい」と。 だから、本書は息子宛てではあるけれど、多くの悩める人が読んでもたくさんの気づきを得られるものになっているのだと思います。幡野さんのメッセージが詰まった手紙のような一冊。親であること、生と死、優しさ、仕事......皆さんも幡野さんの「言葉」を通して自身を見つめ直してみてはいかがでしょうか。










































