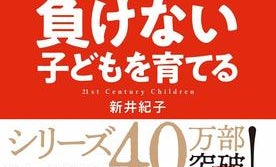山口県で起きた連続殺人放火事件。限界集落の闇にルポライターが単身で挑む!
2013年の夏に起きた「山口連続殺人放火事件」を皆さんは覚えているでしょうか? 山口県周南市のわずか12人が暮らす限界集落で、住民の一人のある男性が一夜にして5人を殺害し、被害者宅2軒に放火したという事件です。 それから3年が経ち、世間の人々の記憶から事件のことが消えかかっていたころ、ある雑誌から「この地区で戦中に夜這いの風習があったかどうか確かめてきてほしい」という依頼を受けたフリーライターの高橋ユキさん。この記事自体は最終的にはお蔵入りとなってしまうのですが、自分の足で村を歩き住民たちに取材をする中で、彼女はある不穏な噂を耳にすることとなります。 先述の連続殺人放火事件が起きた際、逮捕された保見光成の自宅のガラス窓に貼ってあった「つけびして 煙り喜ぶ 田舎者」という川柳は大きな注目を集めました。マスメディアではこれを「放火をほのめかす貼り紙」として決意表明や犯行予告的な意味合いで取り上げていましたが、事実とは異なることを高橋さんは最初の取材時に知るのです。それは、この事件以前にも村では放火が幾度かあり、保見はそのことを川柳にしたのではないかということ。そして、以前の放火犯は保見ではないと村人たちは口をそろえて言うのです。 なんとも不気味で不可解な話に、高橋さんはこの村の正体を知るべく、独自でさらなる取材を続けることを決めます。 陸の孤島ともいうべき閉ざされた村、住民たちによるうわさ話、血なまぐさい事件の数々......まるでミステリー小説の筋書きを見ているようですが、これはフィクションではなくリアルなできごとだというのが一層、読み手の背中をゾクリとさせます。怖いのに、続きが気になってページをめくる手が止められない......! 事件の詳細を知らない人の中には、「妄想性障害を患っていた保見が、住民たちからうわさ話や嫌がらせをされていると勝手に思い込み、それがエスカレートして犯行に及んだ」と思っている人も多いかもしれません。しかし、それは保見の思い込みではなく、住民たちの間では名指しで口にしあうようなうわさ話が存在していたことは事実であり、あるシステムによってうわさ話は何倍にも増幅されて広まっていたことが本書には記されています。 保見は2019年7月に死刑判決が確定。しかも拘置所にいる間もどんどんと妄想性障害の症状を悪化させていたというだけに、もはや彼自身の口から事件の真相や村の正体について聞けることは永遠にないでしょう。だからこそ、皆さんには本書を読んで、サブタイトルにもなっている「うわさが5人を殺したのか?」という意味を考えていただきたいところです。きっと、これまでの報道などとはまた別の側面から、この事件の一端が見えてくることと思います。