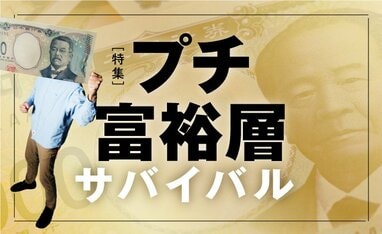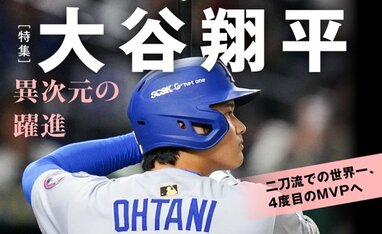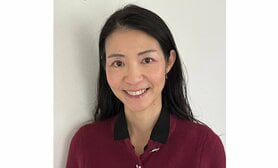女好きの豊臣秀吉、実は男性不妊だった!? 現代の医師が診断
歴史上の人物が何の病気で死んだのかについて書かれた書物は多い。しかし、医学的問題が歴史の人物の行動にどのような影響を与えたかについて書かれたものは、そうないだろう。 日本大学医学部・早川智教授の著書『戦国武将を診る』(朝日新聞出版)はまさに、名だたる戦国武将たちがどのような病気を抱え、それによってどのように歴史が形づくられたことについて、独自の視点で分析し、診断した稀有な本である。本書の中から、早川教授が診断した豊臣秀吉の症例を紹介したい。 * * * 【豊臣秀吉(1537~1598)】 戦国の三大英傑、信長、秀吉、家康が直属の上司あるいは主任教授だったらどうだろうと思うことがある。信長はまず却下。家康もCEOや学長、あるいは大きな学会の理事長には間違いなくなるだろうが、あまり楽しい毎日は望めそうにない。 その点では、豊臣秀吉が最高だろう。もっとも、天下人になるまでという但し書きが入る。 ■サクセスストーリーと天下人の病 木下藤吉郎(幼名・日吉丸)、後の羽柴秀吉は天文6年2月6日(1537年3月17日)、尾張国愛知郡中村郷で足軽木下弥右衛門の子として生まれた。寺の小坊主や行商人を経て当初、今川家家臣松下某に仕えるも出奔して、織田信長に仕え頭角を現した。本能寺の変で信長が明智光秀に討たれると「中国大返し」により光秀を破った後、信長の嫡孫・三法師を擁して信長後継の地位を得た。朝廷から豊臣姓を賜り、関白・太政大臣として天下統一を果たした。巨大な大坂城を築き、太閤検地や刀狩令、惣無事令、石高制など国内統治を進める一方、文禄・慶長の二度にわたって朝鮮に出兵、その最中に、慶長3年8月18日(1598年9月18日)幼い秀頼を徳川家康ら五大老に託して病没した。 「矢作川での蜂須賀小六との出会い」「墨俣一夜城」や、「軍師半兵衛との出会い」「賤ケ岳七本槍」や「小牧・長久手の合戦」「小田原連れ小便」「黄金の茶室」「醍醐の花見」など、秀吉のエピソードは小説やドラマであまりに有名である。最底辺から身を起こし、上司・同僚・部下に気を使いながら順調に業績を上げて出世するというサクセスストーリーは、高度成長期の日本人の共感を得たに違いない。