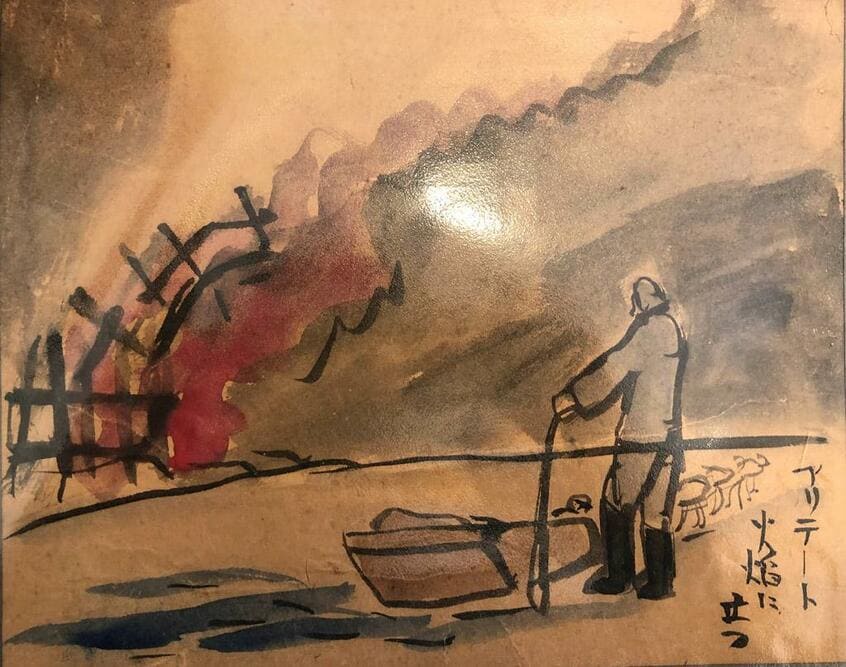
自分が書き手だったら、あるいは編集者だったらばどうしただろうか? それでも収容所の仲間たちが、分担して暗記して、遺書を持ち帰るという行為自体にモジミは感動したはずで、そのことを細かく聞いて、戸叶のことも書いたような気がする。
現在87歳になる長男の顕一の書いた本には、他にも、社会主義者だった山本が、軍部がいやでいやでたまらずしかしそのことは外では口にできない鬱屈から、満州では酒に溺れ家で暴れたこと、まだ幼くて泣き止まない顕一を「生きていたいと思うなら、意志の力を振り絞ってピタリと泣き止むのだ!」と包丁の刃を顕一の首に押し当てたこと、などシベリア抑留前の屈折した幡男についても正直に書かれてある。
遺書が実は届いていたことについて、「辺見さんは、編集者をも騙したのか!」と藤沢は天を仰いだが、私の好きなアメリカのジャーナリスト、ハリソン・ソールズベリーは回想録でこんなことを書いている。
<人生におけるごく単純なことであっても、真実というのは多面体であって、光をさまざまに屈折するガラスのようなものである>
ノンフィクションはそのガラスを照らす光だ。またひとつ、新たな光が「ラーゲリからの遺書」に照らされた。
下山 進(しもやま・すすむ)/ ノンフィクション作家・上智大学新聞学科非常勤講師。メディア業界の構造変化や興廃を、綿密な取材をもとに鮮やかに描き、メディアのあるべき姿について発信してきた。主な著書に『2050年のメディア』(文藝春秋)など。
※週刊朝日 2023年2月10日号








































