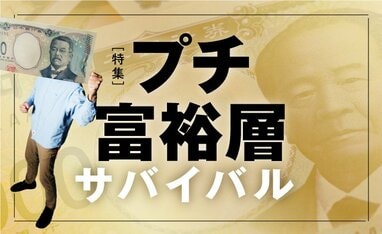切明は、被服支廠のほか、銃火器や弾薬などを製造・保管する兵器補給支廠、人や馬の食料の生産、貯蔵をする糧秣(りょうまつ)支廠でも働いた。兵器補給支廠は、被服支廠の北東部に隣接し、少し離れた所に糧秣支廠があった。「三廠」の物資は、旧国鉄宇品線で宇品港(広島港)に運ばれ、兵士とともに、朝鮮半島や中国大陸の各部隊に輸送された。
「広島は日清戦争から第2次世界大戦の敗戦まで、侵略戦争の出撃基地でした。戦争のたびに全国から兵士が集められ、戦地へ出発していったのです」
そう語るのは、被爆前の広島を研究している『軍都廣島』の共著者、清水章宏。宇品には、30万人の部隊と1千隻以上の大型輸送船を有する船舶司令部があり、兵站を一手に担っていた。
いまではこうした実態を知る市民は少ない。保全の会代表の土屋時子は「私たちも被服支廠問題に取り組んでから、身近に感じ取れるようになってきたのです」と話す。
土屋は昨年6月、被服支廠の保存活動に取り組む若者2人と「Hihukushoラジオ」というインターネットラジオを立ち上げた。番組は1時間で月2回程度の放送。ゲストを招いて、被服支廠について建築、文学、芸術、歴史など様々な観点から話を聞く。
■原爆ドームだけでは被爆は語り尽くせない
メンバーの一人で被爆3世のシンガー・ソングライター、瀬戸麻由は、隣の呉市出身。被服支廠のことは数年前まで知らなかった。
「まず巨大さに驚き、陸軍の力の大きさを初めて肌で感じました。被爆前の広島を想像できるようになりました」
瀬戸は、被服廠を切り口にいろいろなテーマで話ができて面白いという。
広島を原爆ドームという「点」だけでなく、他の場所とつながった「線」や「面」で捉える必要があると言うのは広島大学森戸国際高等教育学院特任教授の河西英通だ。
「被服支廠の保存ができれば、被爆樹木、被爆橋梁(きょうりょう)など、ばらばらに存在している被爆の記憶を結びつけ、『広島回廊』として、つなげることができます。被服支廠はその要衝なんです」