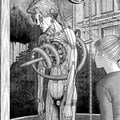さらに秦准教授の試算では、20年間で、全国の浸水想定区域内の人口は4.4%増の約3540万人。世帯数は、約1520万世帯で、25.2%と大幅に増えた。世帯数が増えたのは、核家族化によって住宅が必要になっているからだという。
■大都市でもリスク
しかしなぜ、浸水リスクの高い場所で、人口も世帯数も増えたのか。秦准教授は、3点考えられると話す。
「まず、ダムや堤防といった河川整備が進んだ。次に、60年代の高度経済成長期から2000年代ぐらいまでは比較的気候が穏やかだった。3点目は、中心市街地は土地の流動性が低く権利も複雑で大規模開発ができない。こうしたことから、従来は人が住まなかった浸水想定区域が宅地化されて家が建てられ、人が住むようになったのです」
浸水リスクは地方だけでない。
秦准教授の試算では、世帯数変化率のトップは福岡で38.4%、次いで東京(38.2%)、滋賀(38.1%)、神奈川(35.2%)と大都市を中心に増えている。秦准教授は言う。
「特に東京は、明治以来、人口が増え続けた。滋賀は大阪や京都のベッドタウンで、神奈川も東京のベッドタウンです。人口が増えてゆき中心部に住む場所がなくなったため、今までは住んでいなかった郊外の浸水想定区域に家を建てていったのです」
一人ひとりができる浸水対策は何か。秦准教授は、まずこれまでとは違う雨の降り方が常態化していることを認識することが大切だとして、こう語る。
「基本的には早めの避難。その上で、浸水想定区域に住む場合は住宅をかさ上げしたり、広域で浸水する地域は脱出用ボートを備えるなど対策をとることが大切。また、浸水による経済的損失は大きいので、水害保険に入っておくことも重要です」
(編集部・野村昌二)
※AERA 2021年8月30日号より抜粋