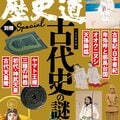* * *
七尾城(石川県)
越後の龍・上杉謙信も攻めあぐねた城
七尾城は、能登守護畠山氏の居城である。この畠山氏は、室町幕府の管領を務めた畠山氏の一族であった。
七尾の地名は、石動山に連なる松尾・竹尾・梅尾・菊尾・亀尾・虎尾・龍尾という七つの尾根に由来する。海陸交通の要衝で、古代には国府がおかれていた。
七尾城は、麓からの高さが250mほどの城山に築かれている。城山の頂上に本丸を配し、主郭部は本丸のほか、二の丸・三の丸・西の丸・調度丸・遊ゆ佐さ屋敷・温井屋敷・桜の馬場などの曲輪群が尾根上に連なる。ちなみに、曲輪の名称については、七尾城も江戸時代の記録に基づいており、戦国時代の呼び方は定かではない。それはともかく、要所には桝形虎口が設けられるなど、防御力は高かった。

天正五年(1577)に七尾城が越後の上杉謙信に包囲されたとき、遊佐続光・温井景隆ら重臣は、織田信長の支援を受けて徹底抗戦しようとする長続連の一族を殺害し、降伏開城した。その後、織田氏が七尾城を奪還し、新たな城主となった前田利家が付近の小丸山に新城を築き、廃城となっている。
城跡は広く、現在整備されているのは城の一部に過ぎない。主郭部から枝分かれして延びる尾根筋にも曲輪が設けられていた。さらに整備が進めば、その全容をうかがい知ることができるだろう。
* * *
洲本城(兵庫県)
壮大な石垣が残る淡路水軍の拠点
洲本城は、戦国時代に三好氏の家臣であった安宅治興が築いたという。安宅氏は淡路水軍を率いており、洲本城は水軍の城だったことになる。天正十三年(1585)、羽柴秀吉の命により脇坂安治が城主となり改修し、四国平定における水軍拠点ともなった。
城は、麓からの高さが130mほどの三熊山に築かれている。東側は海、南側は山続きで、北側は断崖絶壁というまさに天然の要害であった。

本丸は三熊山の山頂におかれ、その周囲に設けられた東の丸や南の丸などの曲輪群で主郭部を構成。主郭部は眺望にも優れ、紀淡海峡や遠く堺や和歌山方面も望めた。また西側に設けられた西の丸は南の乙熊山からの攻撃を想定した出丸であり、敵が主郭部を攻撃した際には、挟撃することが可能だった。
本丸には天守もあり、主郭部での戦闘が想定されていた。ただし、居館は山麓にあったため、北側斜面の東西には、登り石垣が構築されている。この登り石垣によって、山麓の居館部分と山上の主郭部を一体化していたのである。

元和元年(1615)の大坂の陣後、阿波の蜂須賀至鎮が淡路一国を加増され、洲本は蜂須賀領となる。このとき山上の主郭部は廃され、洲本城は山麓の居館のみとなった。