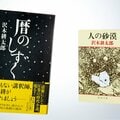「オケラのカーニバル」の意味は、文字どおりオケラ(一文なし)のアマチュア多田さんが、航海に出るその晴れの期間を沢木が「カーニバル」と名づけたのだった。
その沢木のルポで描かれた人柄そのままに、多田さんはメーターを切った深夜のタクシーの車内で、ぽつりぽつりと私たちに話しかけてくれた。
結局、第三便が出たのは、1992年の10月のことだった。当時私はコロンビア大学に留学していたからニューヨークでこの第三便を読んだのだろう。しかし、えらくがっかりした記憶がある。第一便、第二便にあったような、熱がない、そう感じたのだった。
今考えてみると、そのときの自分は、沢木さんが26歳で香港の喧騒やカルカッタの深遠に熱狂していたのと同様の「熱い旅」をしていた。
インディアナポリスという街を駆けずりまわり、会社の利益至上主義の中で職場を追われる調査報道記者たちの話に、心震わせ、それを一本の英語のノンフィクションにまとめようとしていた。
そうした旅のまさに途上にあったことで、欧州が中心の第三便は、響かなかったのかもしれない。
ところが、今回読み直してみて、第三便が静かにしみじみと胸に迫ってきた。
第三便はようは「どう終わるか」という話。
<ここではない、ということだけははっきりしている。ここではない。ここではないのだ。>
<危ない、危ない、という声がどこからか聞こえてきた。このままでは永遠に汐(しお)どきを失ってしまうぞ、と>
2022年の現在、自分は、深夜のタクシーの中で出会った多田雄幸さんの歳を越えてしまった。あのとき、多田さんは57歳。
私がコロンビア大学に留学する前の1991年3月、多田さんは、レースを途中で棄権し、シドニーのホテルで自殺している。そのことを全く覚えていないのは、まだ20代だった自分が、まさに「熱い旅」に出かけようとしていたその時だったからだろう。
が、坂本さんも麻木さんも、私も、「旅の終わり」を意識する年齢にさしかかろうとしている。
で、あるからこそなのだ。
麻木久仁子さんは、先のツイートの後に、こんなメッセージを送ってきてくれた。
「嗚呼。旅は終わりませんね。終わらせてくれません。歩み続けるしかないようです」
汐どきを失ってもいいではないか。
今月末に『天路の旅人』(新潮社)を出版し、朝日新聞の土曜別刷りbeに新作『暦のしずく』の連載を始めた沢木さんは、そう言っているような気がしている。
我らの旅は終わらない。遠くから来て遠くまで行くのだ。
下山 進(しもやま・すすむ)/ ノンフィクション作家・上智大学新聞学科非常勤講師。メディア業界の構造変化や興廃を、綿密な取材をもとに鮮やかに描き、メディアのあるべき姿について発信してきた。主な著書に『2050年のメディア』(文藝春秋)など。
※週刊朝日 2022年10月28日号