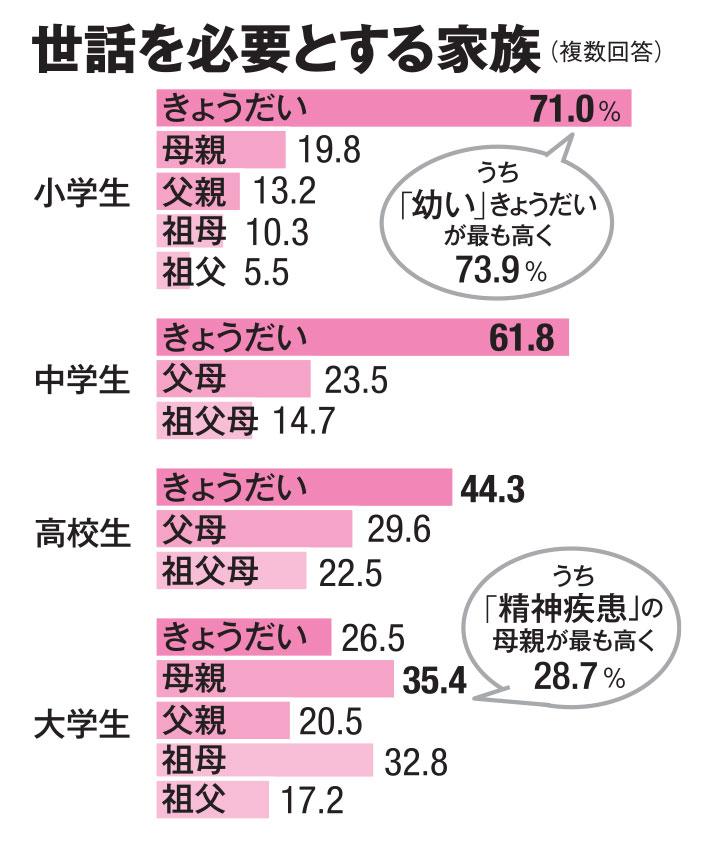
家族の介護やケア、家事などを担っている子ども「ヤングケアラー」。深刻化すると進学を諦めるなどの影響もでる。それだけに早期発見が重要だが、そもそも誰がヤングケアラーなのか把握しにくい問題が立ち塞がる。どのように気付き、必要な支援は何なのか。現場の声を聞いた。AERA 2022年9月19日号の記事を紹介する。(前後編の後編)
* * *
「見えないヤングケアラー」に気付ける場として期待されているのが、子どもが多くの時間を過ごす学校だ。神奈川県教育委員会は教職員向けに、支援の流れや早期発見のためのチェックリストを記載した資料を作成し、ネットで公開もしている。
だが、実際にヤングケアラーを支援したことがあるスクールソーシャルワーカー(家庭や学校、支援機関と連携し、問題解決を図る専門職、SSW)の朝日華子さんら3人のSSWに話を聞くと、全員が「教職員が早期に気付くことは容易ではない」との認識だった。
その理由として、ヤングケアラーという自覚があっても特別扱いされたくないと考える子どもが多いことや、個人情報保護を尊重するあまり、教職員が子どもの家庭内の状況を把握するのが難しくなっている点を挙げる。
■「将来の選択肢」が人生から抜け落ちる
そのため、学校からSSWに相談が来るのはケアによる影響が不登校という形で表れるようになってからになりがちだ。だが、そのタイミングでは、すでにケアが長期化しているなど、問題が複雑化しているケースが多いという。
「私たちに学校から相談が来て、保護者や子どもに聞き取りをする過程で、ようやくヤングケアラーであることに気付くことも少なくありません」という朝日さん。「幼い頃からケアをしているせいか、中学生や高校生になるとケアのベテランのような雰囲気がある子どもも多い。ケアが長期化して、それが日常的になると、保護者が外部の介入を嫌がったり、責任を感じて子どもが周りに相談しづらくなるなど、支援がスムーズに進まないこともある」と指摘する。





































