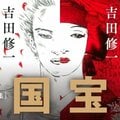それは実学とか虚学とかではなくて、人間らしい気持ち、感情とつながれるかどうかということなのかなとも思う。東大で一番思い出に残っている授業は、「自力で富良野に来たら単位あげる」という授業でしたと伝えたら、養老先生が目を輝かせて、「あの先生のいた頃だよね!! 行った?」と。うれしかった。人間らしい気持ちの共有。
物理が好き、と養老先生に伝えたら、あれは哲学だよねと盛り上がった。机を押すと、同じ強さで机が私を押し返している。これが物理という学問なのだ。学問はロマンというエッセンスが必要だと自分は思う。
養老先生は実験動物が、野生と違って冷暖房完備で退化していく、そして、人間も退化していると指摘されていた。とにかくイレギュラーに弱いんだよね、と。
戦争が起こり、地震も多発する中、そのイレギュラーへの危機意識をどこか他人事にしていてはいけない。野生の人間であれば、国家などと言っていないでどう生きるだろうか。
昨今、ビジネスに使えるかどうか、すぐお金になるのか、そうでなければその教育が無駄という風潮もみられる。養老先生と話していてやはりそうではないと実感した。
無駄はロマンであり豊かさ。野に生きる知恵につながっていく。いろんな物差しがあるということ。その物差しは自分で生きながら作るもの。それは自分の人生だから。
ルソーの「自然に帰れ」を先生と話しながら思い出していた。
※AERA 2022年5月2-9日合併号




![AERA (アエラ) 5/2-5/9 合併号【表紙: 田中圭 】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41OlnfE9BWL._SL500_.jpg)