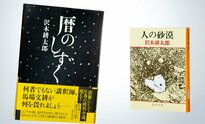昔、木村伊兵衛さんは、スナップショット向きのカメラとして、次の三つの条件を挙げました。
(1)操作が迅速にできること
(2)高性能を有すること
(3)携帯性のよいこと
「以上の要求がすべて満たされるカメラはライカを創始とする35ミリ判距離計連動レンズ交換式カメラである」(『アサヒカメラ講座2 スナップ』朝日新聞社、1955年)
これは正解であり、この教えはいまでも生きています。
70年代に写真の学校に入ったぼくも、いろいろな授業で先生たちに「スナップショットはそういうカメラを使うといいよ」と教えられてきました。当然のことながら「やっぱり、スナップショットはライカだぜ」「レンジファインダーカメラだぜ」という空気が学生の間にはありました。
では、なぜライカが代表するレンジファインダーカメラがいいのか、ということを突き詰めて考えると、やはりあの優秀なファインダーに要因があります。
シャッターを切ったときに一眼レフのようにミラーが跳ね上がらないから、被写体の動きを途切れることなく見続けられる、という理屈です。
では、一眼レフでスナップ写真を撮っていて、これまで不自由だったか、というと、不自由ではないんです。どう考えても。
長秒時の露光で10秒、20秒の間、被写体が確認できないのであれば、その違いは明らかですが、ふつうはシャッターを切って、カシャッと音のする一瞬です。どう考えても長い時間ではなく、「常に被写体を見た」と、言い切っていいわけです。

レンジファインダーカメラのほんとうのよさは、ファインダーを通して見ているものと、肉眼で見ているものが一致していて、被写体とリアルに接しているという感覚が得られることです。常に「むき出し」の感覚のままに現場に立っている、という感じです。

それに対して一眼レフは、どうしてもファインダーの中に自分が隠れているような気がする。ファインダー視野の周囲が暗いがゆえに、暗がりというか、カメラの中、後ろに入って被写体を見ているような感覚にとらわれることがあります。映画館の暗がりでスクリーンを見ているようにも錯覚する。こっち側の安全地帯に「隠れている」ような感覚で、レンジファインダーカメラのような「むき出し」感はない。どうしても被写体をそこに映る映画のワンシーンのような感じで見ていることが多く、自分もそこにいるということを忘れてしまうときがあるのです。