
《WISH YOU WERE HERE》Guitar DAVID GILMOUR
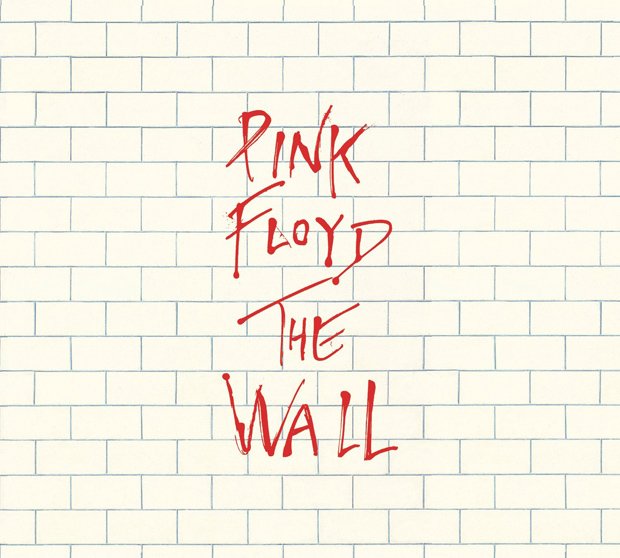
《COMFORTABLY NUMB》Guitar DAVID GILMOUR
今回の26回目をもって終了することとなったこの連載、テーマが「優れたギター・ソロによって愛され、聴き継がれてきた曲」ということで、当然のことながらギタリストたちに焦点を当ててきたわけだが、もちろん彼らは(残念ながら男性ばかりになってしまいました)、ギターを弾くだけの人ではない。その卓越したギター・プレイを核にして質の高い音楽を創造しつづけてきた人たちであり、そのような視点で書きつづけてきたつもりだ。「ギターの神様」や「三大ギタリスト」といった陳腐な表現を一度も使わなかったのは、そういうこだわりがあったからでもある。
まだまだ取り上げるべき人がいるのだが(もちろん女性も含めて)、とりあえずのラストとなってしまった今回の主役は、デイヴィッド・ギルモア。ピンク・フロイドのギタリスト/ヴォーカリスト/ソングライターとして、分裂や活動中止の時期も乗り越え、2014年までその伝説を守りつづけた音楽家だ。昨年(16年)夏には、ピンク・フロイドが1971年に画期的な映像作品を残したポンペイの遺跡で、大規模なソロ・コンサートを行なってもいる。
60年代半ばに第一歩を踏み出したピンク・フロイドは、当時は創作活動の中心的存在だったシド・バレットの精神面でのトラブルが深刻化していったこともあり、67年暮れ、彼の少年時代からの友人でもあったギルモアを迎えている。その後、バレットはバンドを去り、コンセプト固めやソングライティングは次第にロジャー・ウォーターズの手へと移っていく。そして73年には、あの歴史的名盤『ダーク・サイド・オブ・ザ・ムーン/狂気』が生まれ、ウォーターズを中心にしたバンドというイメージはさらに強固なものとなっていった。
ブルースに惹かれ、強い憧れを持ちながらも、あくまでも欧州的な感性でそのエッセンスを吸収していったギルモアは、この間に、ギタリストとしての評価を確立していくわけだが、ウォーターズ中心の創作には、不満も感じていたに違いない。彼は、ただのギタリストではなかったのだから。
『狂気』につづくアルバムの、結果的にタイトル・トラックとなる《ウィツシュ・ユー・ワー・ヒア》は、ギルモアがアコースティック・ギターで弾いていた曲の原型のようなものにウォーターズが興味を持ち、バレットへの想いをテーマにした歌詞を加えて完成させたものだという。また、ほぼ完全にウォーターズ主導で制作された『ザ・ウォール』収録の《カムファタブリィ・ナム》は、もともとはギルモアのソロ作品のために書かれていたものがベースになっているらしい。
そういった逸話からもギルモアの不満が伝わってくるようだが、ともかくそのようにして、彼は2つのマスターピースを手にしたのだった。前者は、アコースティック・ギターを核にしたロックの名曲の代表格と呼んでいいだろう。通奏音を生かした美しいイントロと、そこに乗って弾かれるよく練り上げられたソロは、発表から45年近く過ぎた今も、まったくその輝きを失っていない。後者での長いソロは、「速弾きはしない」タイプのギタリストだからこそ、という感じの独特の緊張感がなんとも印象的だ。
ウォーターズが去ったあとの後期ピンク・フロイドのライヴでも、ソロ・アーティストとしてのステージでも、ギルモアはこの2曲を大切に演奏し、歌いつづけてきた。そしてこれもまた、きわめて特徴的なこととして、基本的にはライヴでもオリジナルの雰囲気を守り、ソロの構成や進行も変えることがないのだが、そのうえで、つねに新鮮なイメージのプレイを聞かせている。それができる人、ということなのだろう。



































