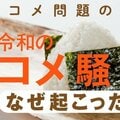石破首相は「生産量に不足があった」
さらに、8月5日の関係閣僚会議で、農水省は検証結果を提示。石破首相は「生産量に不足があったことを真摯に受け止める」とし、「減反政策」を見直し、増産にかじを切る方針を改めて表明した。
「調査を始める前から結果はわかりきっていた。この調査は、流通段階で米の在庫を持つ業者は『悪』だと、やり玉に挙げ、その追及姿勢を国民にアピールする意図しか感じませんでした」(同)
農水省の説明に現場は疑問
これまで農水省は、米の需要見通しに対して生産量が足りていることを根拠に、「米不足は起きていない」との説明を繰り返してきた。今回、「流通の目詰まり」が自らの調査で否定されると、「需要の見通しと実需の乖離」を食糧部会に示している。
「乖離」が大きくなったのは2年前からだ。23年産米は681万トンの需要見通しに対して、実際の需要は705万トン。24万トン上振れした。24年産米は674万トンの見通しに対して、実需は711万トンで、37万トン多くなった(※ただし、現在の算定方法による)。
これに対して、中村さんは首をかしげる。
「2年連続で20万トンを超える需要増があれば、現場はそれを感じるはずです。しかし、そのような実感はありません」
調査結果を受けての説明は?
食糧部会の翌日となる7月31日、記者が農水省に問い合わせたところ、担当者によると、23年産の米の実需の増加には3つの要因が考えられるという。
1つ目は、猛暑による「精米歩留まり」の低下だ。精米歩留まりとは、玄米を精米して表面のぬか層を削り取ったあと、得られる白米の割合のことだ。米は稲の種子だ。猛暑にさらされた稲は種子を守るため、もみ殻やぬか層を厚くする。厚くなったそれを取り去れば、可食部になる白米は当然、小さくなる。そのぶん、農水省が統計で扱う玄米の実需は多くなる。
2つ目は、小麦価格の上昇で、パンやうどん、パスタなどの商品が値上がりしたため、米の需要が増えた可能性だ。
3つ目の要因として、「インバウンド増加の影響も多少はあると考えられます」(農水省の担当者)
だが、報道によると、こうした農水省の分析に対して、食糧部会の有識者からは「エビデンス(科学的根拠)を説明しきれていない」という声が相次いだという。