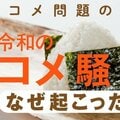農水省の説明「説得力に欠ける」
農業経営学が専門の宮城大学・大泉一貫名誉教授も、農水省の説明は「説得力に欠ける」と指摘する。
たとえば、精米歩留まりの低下について。精米歩留まりは通常90%ほどだ。農水省によると、23年産米は88.6%、24年産米は89.2%で、若干低い程度だった。
「90%弱という値は信じがたい。卸売業者に聞くと、精米歩留まりは80%強と、著しく低下している」(大泉名誉教授)
稲の高温障害によって白く濁った「白未熟粒(シラタ)」や、亀裂の入った「胴割れ米」の割合も増加しているという。そのため、消費者の欲しがる高品質の米が減った。23年産米は、最も品質がよい「1等米」の比率は全国で60.9%で、前年同時期を17.7ポイントも下回った。
「机上の計算」が実態と乖離
「新潟県は特に低く、コシヒカリの1等米比率はたった4.9%しかなかった。米価高騰の原因は、需要に対して単純に生産量が不足しただけだと考えています」(同)
これまで農水省は生産現場に目を向けず、「鉛筆なめなめ、机上の計算で需要見通しや生産目安を決めてきた」と、大泉名誉教授は指摘する。
「だから、ここまで実態と乖離してしまったのでしょう」
実質的に23年産米は「不作」だったのだとしたら、24年は大きく増産しなければならなかった。
「ところが、農水省はこれまでの誤りを認めず、備蓄米の放出を渋り、増産に舵を切れなかった」(同)
だが、ついに8月5日、農水省の提示した検証結果に対して、石破首相が「生産量に不足があったことを真摯に受け止める」と述べたのだ。コメ問題はようやくスタート地点に立ったとみるべきだろう。
今夏は全国的な猛暑が続き、新潟など米どころを含め渇水が報じられている。米をめぐる難局はまだ続きそうだ。
(AERA編集部・米倉昭仁)
こちらの記事もおすすめ 【真相ルポ】「米が足りない」現場の訴えを農水省は握りつぶした 発端は2年前の「猛暑」 1等米がわずか4.9%に