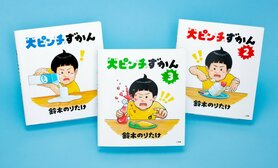日本を代表する企業や組織のトップで活躍する人たちが歩んできた道のり、ビジネスパーソンとしての「源流」を探ります。AERA2025年7月21日号より。
* * *
1997年3月30日、福岡県大牟田市の三井東圧化学(現・三井化学)の大牟田工業所で、三井三池炭鉱の有明坑が閉鎖された。歴史を持つ同市での石炭採掘が、終わる。大牟田工業所の事務部人事課長、45歳のときで、日にちはいまも覚えている。
三池炭鉱は同市や南の熊本県荒尾市などに坑道が延び、江戸時代に採炭記録がある。明治政府の1888年の競売で三井組(三井財閥)が落札し、翌年から三井組の経営となった。新設された三井鉱山による経営で近代化が進んで坑口も増え、大牟田は「石炭のまち」として栄える。
三井鉱山は1933年に東洋高圧工業を設立、1941年に三井化学工業も設立し、幅広い事業を展開させた。ところが、第2次大戦後、エネルギー源の主役の座は石油へ代わり、採炭量は減って、人員整理などが進むと労働組合と会社は争議を繰り返す。60年の労使対立は「三池争議」の名を昭和史に残したほど、激しかった。地域経済は疲弊し、いろいろ摩擦も起きる。
父は炭鉱の技師で、三池争議のときは荒尾市の四山坑の坑口責任者。人員整理で離職をする人たちの働き場を探そうと、走り回っていた。みんなのために「地域を守る」という父の姿が、淡輪敏さんのビジネスパーソンとしての『源流』となっていく。
自分にも起きた炭鉱閉山で生じた離職者の再就職斡旋
有明坑の閉鎖で、自分に同じことが起きた。68年に東洋高圧工業と三井化学工業が合併して三井東圧化学となり、8年後に入社した。故郷の大牟田市の勤務になったのは、有明坑閉鎖の3年前。石炭採掘がなくなれば、様々な協力会社からタクシーに至るまで、多くの人が仕事を失う。再就職の斡旋に、努めた。