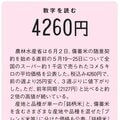今朝はパンを食べました
とはいえ土井さんは、現代の私たちは米だけを食べているわけではなく、味のしっかりついた外国料理や便利な加工食品も食べている。「米離れ」と言われて久しいが、家計における支出(金額)は、すでにパンが米を上回っている。パンを作る小麦は、ほぼ海外からの輸入に頼っている。そんな点も指摘する。土井さんの感覚は柔軟だ。
「私も今朝はパンを食べました。パン食はすでに定着しています。しかし、私たちは何を食べるべきかを考えるべきですね。カレーを作る時は、軽いタイ米のご飯を炊きます。タイ米などの輸入米は日本と同じ米とは考えない、それぞれ別の商品です」
自分の食べものくらい
自然環境危機、世界の食料危機によって「あたりまえにあるもの」が徐々になくなってきている。あたりまえのものとは、空気や水に食料、それに家族の健康、美しい文化……。私たちはあたりまえのものに常に無関心だが、「今」それを意識して守らないといけなくなった。土井さんはそう話す。
「そのためには、日常の料理の意味や和食文化の意味を知ることです。幸せな暮らしは、家族が作って家族が食べるという食事の基本から成ります。家族は自分、自分は家族です。料理して食べることから生まれる情緒が、思いやりを育み、大自然を思い、大切なものを守ることになるのです。台所は地球と繋がっています」
食文化を守ることは一人ひとりの問題で、国にはできない。自分が何者であるかを知ることだと、土井さんは言う。
「『自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ』。茨木のり子さんの有名な詩の一節です。『自分の食べものくらい、自分で考えろ』と言いたい。そんな心でお米に向き合ってみてください。きっといつもよりおいしく炊き上がると思います」
こちらの記事もおすすめ 89歳女性「私の体はお米でできている」 楽しみは軽くよそったご飯と少しのおかず 「かけがえがない」が9割 消費者の思い