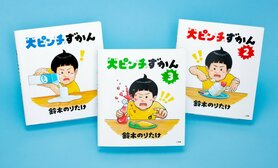古野:義材の存在というのは、政元にとって物凄く大きな変数だったと思います。彼が生き残ったがゆえに室町将軍の家系が2つに分かれてしまう形になっていって、その後の混乱に拍車を掛けたということになりますからね。
ただ実は、義材以前にも室町幕府は義尚の時に2つに割れていますので、16世紀の前半から中盤以降にかけて、室町幕府は2つに割れた流れが存在するのです。
なので義材が仮に政元にちゃんと確保されていて台頭できなかったとしても、その後の混乱のようなものは、また別の形で出現したんじゃないかなとも考えられるのです。決して室町幕府が長く続いたとも思わないですし、おそらく時間の問題だったのではないかと考えています。
ミスター武士道:いつの時代も長く続くと、後継ぎなどどこかでほころびが出てきてしまうのかもしれませんね。義材は政元からすると、もともと敵対していた義視の子ですし、それを迎え入れたという所からして、もう不穏ではありましたね。やはり、もう室町幕府というシステム自体にもう限界が来ていて、それを政元は力技で何とかしようとしていたというように見ることもできるような気がしますね。
古野:そうだろうと思います。例えば六角氏など、以前から守護を務めていたような一族もそこまでのパワーが無かったわけですし、幕府の中における存在感や役割ももうそれほどになかったでしょうから。力技でなんとかねじ伏せられるかもしれない、と思わせるパワーを持っていたのは、もう政元までだったんだろうなと思っています。
ミスター武士道:「オカルト武将」でも触れられていますが、やはり戦乱を治める時ですとか、人々の不安が充満している時代を変える時には、そういうパワーを持った指導者が輝くし、皆がそういう人を求めるのでしょうね。でもその人が結果を出して平和になってくると、「あいつはやばいぞ」と支持を失っていくという……。これはすごく普遍的といいますか、現代でも言えることなのかなと。人間社会の一つの課題なのかなと思いますし、本書で書かれているとおり、「政元を通して今の時代を見る」というのも1つのいい視点になるのかなと感じました。
古野:そういう風に読んでいただけたらとてもありがたいです。500年前の話をして何の意味があるのかと言われることがあるのですが、過去にあった事柄からしか私たちは未来を予想することしかできないので。この時代の事例からさまざまな面で参考や反省につなげられると思いますので、本書もその一つになればいいなと思います。
ミスター武士道:ありがとうございました!
(文・構成/飯塚大和)