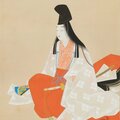メディアにとってグーグルが起こした革命は、検索それ自体にあったのではなく、実は広告の仕組みそのものを変えたことにあった。
それまで広告は、媒体の中身を吟味しながら、出稿するものだった。化粧品は女性誌や、主婦が見る昼間の時間帯、電化製品は家族そろってテレビを見るゴールデンタイム、書籍広告は、新聞の二面の下といった具合に、新聞の広告面やテレビのCMの枠を押さえている広告代理店が広告主の要望にそって、広告の枠を売る。
電通は、テレビで言えばゴールデンタイムの人気番組や、新聞の書籍広告で人気のある二面、三面下の全五段の広告を押さえていることで、圧倒的な力をもっていた。
グーグルやヤフーが2000年代初頭に開発した運用型広告の仕組みは、その電通が持っていた力を根底から破壊した。
この運用型広告は、広告を出した広告主にとっては、どこに配信されるかまったくわからない。アルゴリズムによって個々の消費者それぞれを追いかけていき、もっともクリックをしそうな場所に配信をされる。
広告主はその広告効果を、自分のところの広告が何回クリックされたというクリック数で瞬時に把握できる。
1977年に電通に入社し新聞局に配属された長澤秀行の電通人生は、新聞・テレビを押さえていた電通の黄金期が、プラットフォーマーの登場によって、2000年代以降、もろくも崩れ去るその歴史を目の当たりにしてきたことになる。それはメディアにとってはブランド価値を失うという歴史でもあった。
電通はヤフーをメディアと考えていた
長澤によれば、電通は「鬼十則」で有名な、吉田秀雄(1947~1963年社長)の時代から、メディアを育てるという意識があったという。民放の草創期、広告などとても集まらないという時代に、広告主たちを説得して広告を集めてきたのも電通だった。
そのでんにならって、実は電通はヤフーが日本で創業する1996年、ヤフーにかわって広告を集めるCCIという会社をつくっている。出資比率はソフトバンクが49パーセント、電通が51パーセント。
「日本でヤフーをたちあげたソフトバンクの孫(正義)さんが当時の社長の成田豊のところにきて助けてほしいと頼んだのです。電通はテレビの草創期でも、惜しみない援助をしましたから、この新しいメディアのために一生懸命広告を集めました」(長澤)