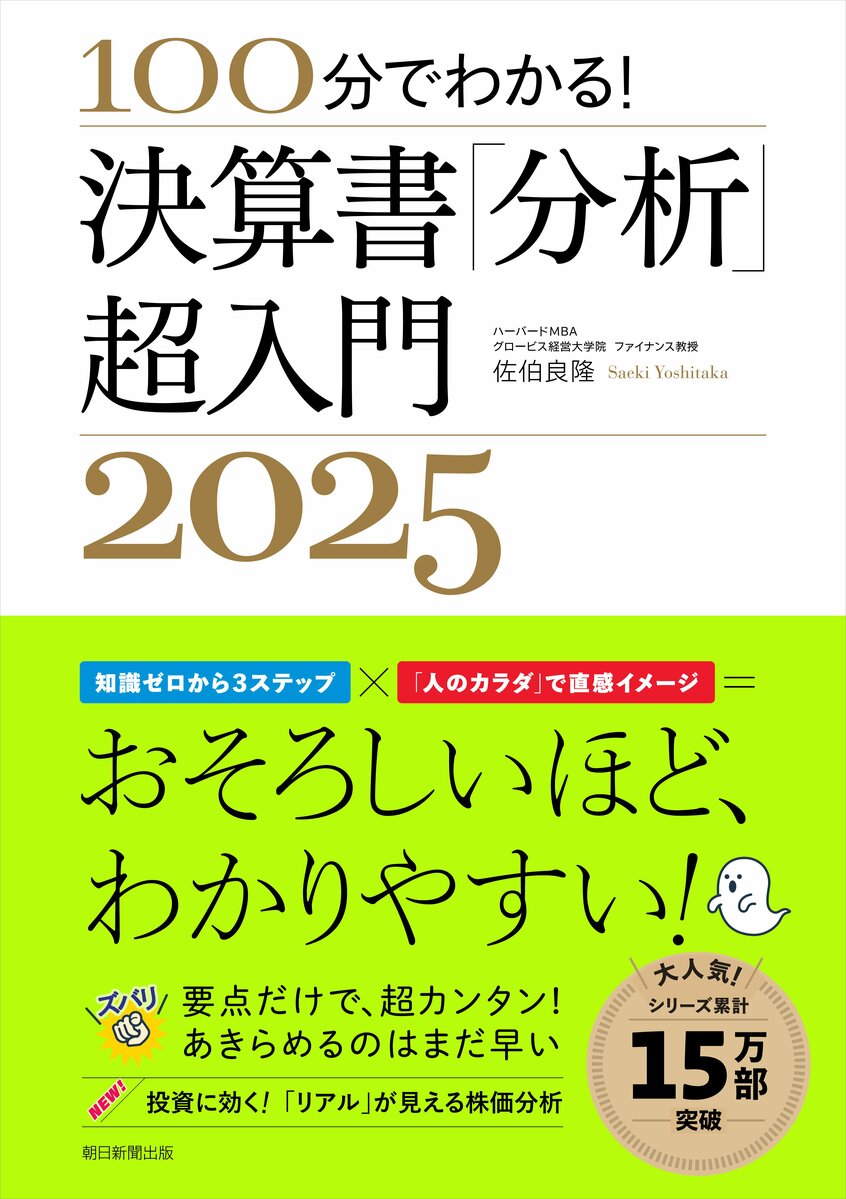ちなみに日本企業の営業利益率の平均値は、製造業で約4.9%、小売業で約2.8%となっています(※)。業界平均よりも高い営業利益率をあげられていれば、優秀な経営ができているといえるでしょう。
さて、この営業利益率に大きな影響を与えるのが、販管費です。例えば、製品を売るために多額の広告宣伝費を投入するなど、販管費が膨らむほど営業利益率は下がります。
ただし広告宣伝費が上昇している場合は、それが新製品の認知度を高めるためなのか、販売に苦戦しているためなのか、理由を探ることが大切です。例年に比べ、大きな変動のある費用については、決算書の「注記事項」に理由が書かれている場合があります。
また、大手製薬会社などは、新薬の開発を行うため、膨大な研究開発費を投入しています。今までにない画期的な薬を生み出し、製品の付加価値を高めることで、販管費が膨らんでも十分な利益を確保できるのです。
このように営業利益率には、各会社が商品を売って利益を得るための「販売戦略」の結果が加味されます。
例えば、高付加価値の商品を販売する会社(業種)は、商品の開発やブランディングにお金がかかるため販管費が膨らみ、売上総利益率に比べて営業利益率が大きく下がることがあります。化粧品会社がいい例です。
一方で、薄利多売型の会社(業種)は、販管費を抑制して利益を確保するため、売上総利益率と営業利益率の差は小さくなります。スーパーがいい例です。
他社比較分析を行う際、我々プロは、業態ごとの差がより少なく、事業からの収益性がわかる営業利益率を重視します。
(※ 2022年度の平均値。経済産業省『2023年企業活動基本調査確報ー2022年度実績ー』を参照)
《好評発売中の書籍『決算書「分析」超入門2025』では、経常利益率、当期純利益率に注目したさらなる収益性分析についても詳しく解説しています》