
70年の万博では、テクノロジー万能主義に対して、岡本太郎が異形の生命パワーに満ちた太陽の塔を創り、人類は進歩していない、調和していないじゃないかというアンチテーゼを出しました。それと同じように、今、2025年の万博をやる上でも、やはりある種のアンチテーゼが必要で、それはAI全盛、あるいはテクノロジーが人間を不老不死にしていくという考え方に対して、基本は生命の有限性の上に立って生命の輝きを考えるべきだと思います。
利己的世界への抗い
福岡:“何々ファースト”という考え方は、非常に利己的な振る舞いで、それを人間は繰り返し行ってきた。
生命全体を虚心坦懐に見ると、ストックよりもフローということが常に優先されています。その中に、何々ファーストという考え方はない。にもかかわらず、人間は利己的に振る舞い、ファーストという閉じた考え方をし、できるだけ自分のためだけにストックしようとしている。
これは生命の基本原理には反していて、現在のさまざまな世界の指導者たちに、もう一度その生命の本来の原理に立ち返って、世界を見つめ直してほしいと願います。トランプ大統領には来日の際、是非いのち動的平衡館に立ち寄ってほしいです。
人類というのはホモ・サピエンスというたった一つの生物種。それなのに、ちょっとした差が大きなものとして捉えられて、肌の色、文化、民族、国というフィクションをつくり出してしまった。本来、一つの種が存続していくことが生命にとって重要なことで、その内部で対立している場合ではない。そういう意味でも、生命全体の利他性というメタ視点をもって言えば、局所的な紛争というのが、愚かなことだということに気づけると思います。
生命としての共通原理というのは、生物も38億年前のたった一つの細胞から枝分かれして、協力しながら、地球環境の中で豊かな生態系をつくってきたわけなので、本来的には対立するべきものではなくて、協力・共生するべきものであるというのが生命の基本原理だというふうに考えるわけです。
やはり生命哲学というものが、何かを考える上での基本的な羅針盤になるため、私は常にそこに立ち返って、世界を見たり、生命を見たり、宇宙のあり方を考えるべきだと思います。
死を肯定的に捉える
福岡:死というのは、最大の利他的な生命の振る舞いです。一般的には避けるべきことというふうに思われがちですが、メタ視点で見ると、死ぬことによって、ある生物が遷移していった日を別の生物に手渡すということが新たな変化を生み出すきっかけになっている。それが連綿と続いてきた。そういう意味で、肯定的に捉えることができるのではないかというメッセージを、いのち動的平衡館で体感してほしいと思っています。
(構成/ライター・米澤伸子)
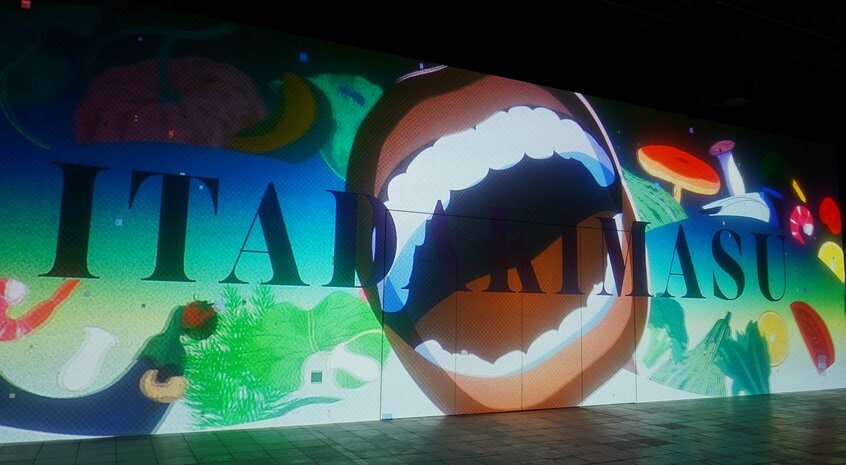
※AERA 2025年5月5日-5月12日合併号
こちらの記事もおすすめ 小山薫堂 50歳で「1カ月休暇」をとった理由






































