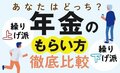やはり2000万円は必要じゃないか……と思った読者は早まるなかれ。これはあくまで65歳の高齢夫婦も90歳の高齢夫婦も含めた平均的な値。年齢別の支出の傾向を分析すると、さらに必要になる蓄えは小さくなる。
「高齢夫婦世帯のひと月の赤字を細かく見ていくと、60代に比べて85歳以上の世帯は4分の1程度に減っています。人間は年を取るほど支出が減っていくから、赤字が減っていくのです。その年齢層別の支出を勘案し、さらにインフレ率2%を前提に試算してみると、高齢夫婦が30年間生きるために必要な蓄えは1200万円でした。物価の変動に合わせて年金の給付水準が徐々に減少していくことも念頭に入れても、1400万円あれば十分事足りるでしょう」(同)
夫はバリバリ会社員として働き、妻は家庭を守る――そんな“平均的”な家庭であれば、「老後に備えて蓄えておくべき資金は1400万円」が正解となる。一方で、夫婦ともに会社勤めをしてこなかった夫婦は、当然のことながら必要になる蓄えは大きく増える。
自助努力による備えは重要
年金制度を端的に示す際に用いられる夫婦の“モデル年金”は、夫と専業主婦の妻の老齢基礎年金に夫の老齢厚生年金を足したもの。昨年度のモデル年金は約23万円。一方、24年(令和6年)の家計調査結果によると、65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支は2万7817円の赤字だった。
仮に、夫婦ともに基礎年金のみの場合は14万円弱にしかならないためにさらに赤字は大きくなる可能性がある。もらえる年金は人によってまちまちのうえ、インフレも進む中で、自助努力による備えは重要になる。
ファイナンシャルプランナーの岩城みずほ氏は「働き方は多様化しているし、お金の使い方などもさまざまなので、個々に必要な老後資金を試算することが重要」と話す。