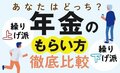追い打ちをかけるように、昨年は「4000万円問題」へとバージョンアップした。足元で進むインフレの影響を加味すれば、今後必要になる老後資金は2000万円でなく4000万円だ、とメディアが報じるようになったのだ。
「5年で倍に増えたら、これからまだまだ増えるのでは?」
そう不安に駆られる国民が急増したのは間違いない。先の男性も、その報道後に「投資経験ゼロだったけど、新NISAを始めた」と話す。
だが、「4000万円問題」は国民をミスリードしている。第一生命経済研究所の永濱利廣・首席エコノミストは「そもそも2000万円問題も誤った認識だ」と話す。
「2000万円問題は、2017年の家計調査で高齢夫婦無職世帯の月の収支が5万4520円の赤字だったため、それが30年ずっと発生すると2000万円の蓄えが必要になるとして公表されたものです。ところが、その世帯の収支は2020年には月1100円ほどの黒字になり、勝手に2000万円問題は解消されたんです。コロナ禍で支出が減った影響と考えられますが、2023年のデータで見ても月の赤字は3万8000円弱に縮小している。これを30年分にすると1400万円弱になる」
約2030万円
つまり、「老後1400万円問題」へとスケールダウンしているのだ。ただし、インフレを加味すると、必要になる金額は少々変わってくる。
「昨年話題になった『4000万円問題』は、『3.5%のインフレが30年続いたら』という仮定のもと算出した金額です。しかし、日銀は今年1月に物価見通しを若干引き上げましたが、25年度は2.4%で、26年度は2%という予想。つまり、3.5%のインフレが続いたらという仮定は、明らかに過剰なのです。日銀の物価目標に合わせて、安定的に2%のインフレが進むなかで毎月3万8000円の赤字(2023年の高齢夫婦無職世帯の月間赤字額)が発生すると仮定した場合、30年間で必要になるのは約2030万円になります」(永濱氏)