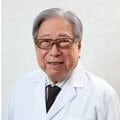一方、介護が必要になったら配偶者に依頼したいと回答した人は3割程度いるが、性別でみると、男性では50・8%、女性では12・5%と、男女で大きな差がある。しかし男性も特にこの20年間、長生きして亡くなる人の割合が増えている。2000年に亡くなった男性のうち、80歳以上だった人は33・4%しかいなかったので、妻はまだなんとか夫を介護できる年齢だったが、2022年には57・5%と過半数が80歳以上で亡くなっている。男性の長寿化で、妻はもはや夫を介護できる年齢ではなくなっており、現実は、介護サービスに頼らざるを得ない。
死後の処置は家族の役割で、ノウハウを学校で学んでいた
亡くなるときも、家族から専門家への移行は同様だ。少し古いが、大正時代の家政学書『家政講話』には、臨終が近づいたら、寝床をきれいに整頓し、静かに臨終を遂げさせ、医師の死亡診断を経て、衣類を脱がせて消毒薬で全身をぬぐい清めるといった手順が記載されている。
また、高等女学校などで使われた『応用家事教科書』にも、呼吸が切れたら医師の検診を受け、遺体を仰向けにして目と口を閉じ、消毒薬で全身をぬぐい、衣服を着替えさせ、白布で覆うという手順が細かく書かれてある。死人の看取りや死後の処置は家族の役割であり、そのノウハウを学校で学んでいたのだ。
しかし病院で亡くなるのが当たり前になると、湯かんをしたり、服を着せ替えたりという作業は、家族の役割ではなく、外部サービス化されていった。
私の曾祖母が祖父母の自宅で40年ほど前に亡くなった時、水に湯を足して「逆さ水」を作り、みんなで遺体を拭き、曾祖母が生前に自分で縫っていた死装束を着せたことを覚えている。その時代は、逆さ水で全身をきれいにすることを「湯かん」と呼んだが、昨今では、葬祭業者が、遺体を湯舟のなかに入れ、体や頭髪を洗うことを指すようになっている。
病室で亡くなる人が増えると、看護師が故人に装着されていた医療器具や管をはずし、排泄物などを処理し、全身をアルコールでの清拭をおこなうので、それを「湯かん」としたケースも多かったが、昨今では、葬祭業者の熱心な売り込みもあり、「最後のお風呂に入れてあげよう」と、葬祭業者に湯かんを依頼する遺族も少なくない。湯かんの費用は5万円から10万円程度かかるが、葬祭業者にとっては、貴重なオプションサービスとなっている。