こういう人たちは、脳がつねに働いている状態で、休まっていません。「デフォルト・モード・ネットワーク」といって、ボーっとした状態の脳がおこなっている神経活動が重要視されています。
たとえると、自動車のエンジンはかかっているけれど、走行していないアイドリング中のような状態です。現代では、意識的にそういう状況を作らないと、ボーっとすることも難しくなってきているようです。
漢方的な理想の姿と真逆になっている
江戸時代の儒学者であり、医師でもあった貝原益軒は、『養生訓』で、健康で長生きするためには「こころはつねに平静を保ち、からだはよく動かすこと」が理想の姿だと書いています。現代人の多くは、まさにそれとは真逆の姿になっているのかもしれません。「疲れている」と受診された患者さんからよく話を聞くと、確かにこころは疲れているけれど、からだは全く疲れていないということもよくあります。
今こそ社会そのものを見直し、改めて幸せとは何かということを考え直すべきときがきているのではないでしょうか。
日々蓄積していくこころの疲れ、小さなストレスというのは、自分では気づきにくいものです。しかし、そこで放置して小さなストレスが蓄積していくと、やがてストレス反応の許容ラインを超え、不安、不眠、抑うつなどの症状が出始めます。
ストレスはうつやパニック障害、不眠症などこころの不調だけではなく、がんや免疫疾患、過敏性腸症候群(IBS)、糖尿病の悪化、冷え症など、さまざまな病気や不調の原因となるのです。
病気を発症する前に、小さなストレスの段階で、自分で気づき、対処していくことが心身の健康を維持するために大事なことです。
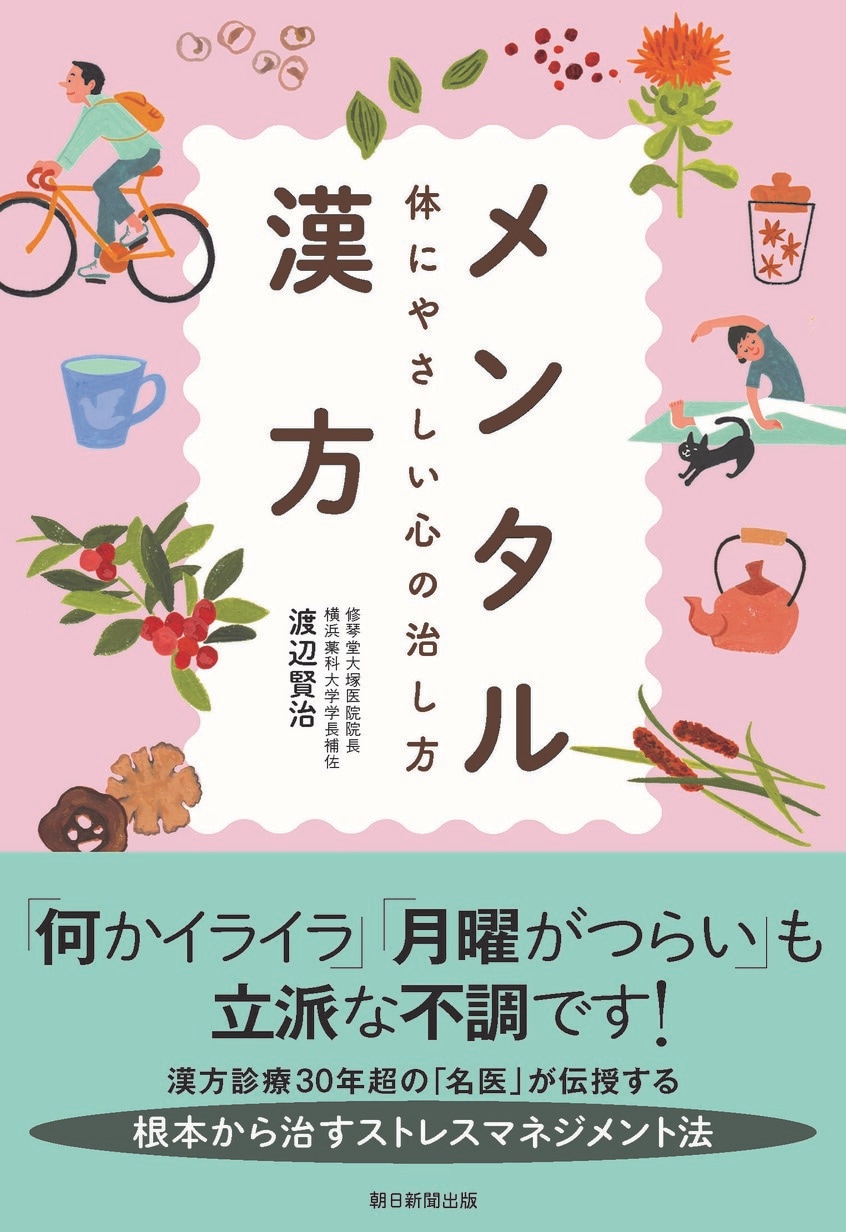
※『メンタル漢方 体にやさしい心の治し方』(朝日新聞出版)から一部抜粋
こちらの記事もおすすめ 「“月曜日がつらい”も立派な不調」と元慶應大教授 過度なストレスがかかると心の不調に








































