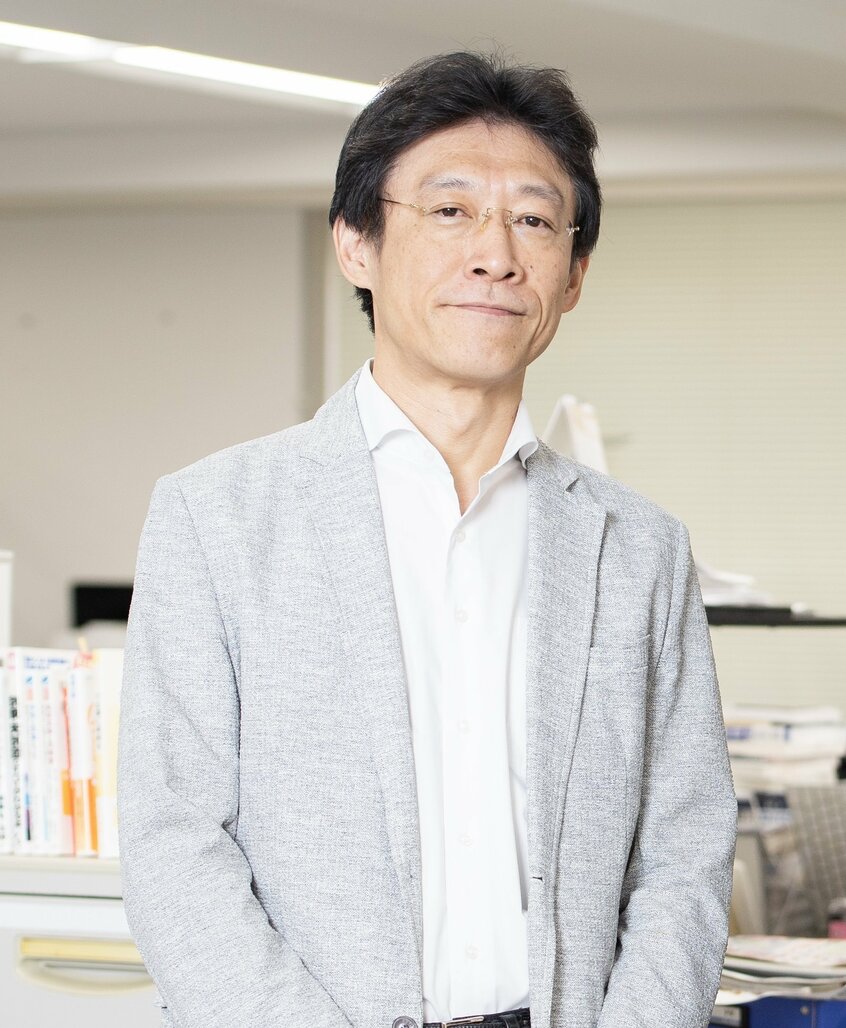
現常務の麻生が語る。
「実は2023年4月に週刊ダイヤモンド事業室をつくって、ここで、週刊ダイヤモンドの収支を経費構造からもういちどあらいなおしていったんです。その中で書店で売れる特集と、デジタルサブスクで有料会員数を獲得する特集がまったく違うということが問題になりました。書店では、シニア向けの介護、病気、相続といった軟派の特集がうけるが、デジタルサブスクでは、かつてのダイヤモンドが得意だった産業・企業の特集がうける。ひとつの編集部が両方やるのは、リソースの問題として大変だ。いっそのこと、今伸びているサブスクに特化しようということになったんです」
現在、週刊ダイヤモンドの書店売りは、1万6862部。紙の定期購読での部数は3万1779部。書店売りでの部数は年々減っており、扱う書店数も限りがあったという。
しかし、そうは言っても、7億6000万円強の売上が、書店売りをやめればゼロになる。
私もかつていた会社で経験があるが、「下ちゃん、8億の売上を捨てられないよ」と通常であれば、ここでストップがかかる。
書店売りをみていたのは別の局の別の取締役だったが、書店売りを辞めることにGOサインを出したのだという。
書店や取次の反発はないのだろうか? こう聞くと麻生は、こう答えた。
「丁寧に説明をしていきます。うちは書籍が強い。こちらで儲けてください、と」
サブスクができるのは経済誌だけなのか?
定期購読やデジタルサブスクでは、読者の属性(年収や会社での役職など)が申し込み時に捕捉できるという強みがある。麻生によれば、企業の管理職が圧倒的に多いのだという。これが、企画広告で単価の高い広告がとれる源泉になっている。また、デジタルの場合だと、読んだ特集によってターゲティングする広告の出し方ができる。
出版社でのサブスクの成功例では、他には、東洋経済新報社の会社四季報のデジタル版「会社四季報オンライン」がある。こちらは、2024年6月の同社の発表によれば、契約者数は3万5000人を突破したという。
こうならべていくと、経済に特化した版元でなければデジタル有料版を成功させることは難しいのか、という声が出てきそうだ。


































