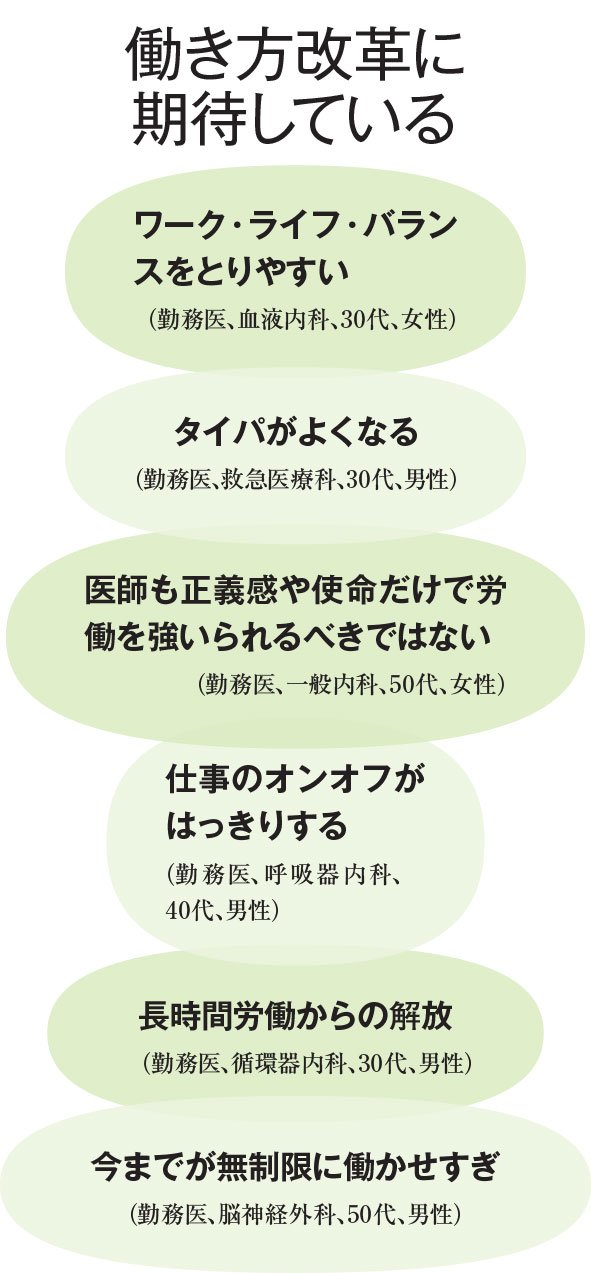
「勤務時間は午前8時30分からですが、患者さんが手術室に入室するのも8時30分。その時間に出勤するなんて、あり得ないじゃないですか」
7時30分には出勤し、手術前のカンファレンスを行い、準備をする。ただ、労働時間の超過で働けない事態は起きていない。
「帳簿上、勤務時間を削っているのではないかと思います」
サービス残業は「自己研鑽」
女性医師が働く大学病院では、「ビーコン」という小型の機器を、院内の滞在時間を把握するために医師に持たせている。
「ビーコンには残業した証拠が残ります。けれども残業申請できず、残業時間を自己研鑽と申告せざるを得ない医師もいます」
残業には所属長への申請が必要だ。麻酔科は手術時間が明白な証拠になるので申請しやすいが、手術のない診療科では申請しづらい。自己研鑽という名のもと、サービス残業が横行しているという。
医師の労働時間の制限により、地方医療への影響も懸念される。大学病院が医師を派遣できなくなる恐れがある。
一方、医師にとって大きいのは、収入減だろう。たとえば、大学病院の若い勤務医にとって、派遣先=バイト先。労働時間を制限されれば収入が減る。アンケートでも不安の声が上がった。
バイトが1カ所なくなるだけで困る
「アルバイトできない」(精神科、20代、男性)
「給料が下がるのではないか」(一般内科、30代、男性)
ある大学病院の女性医師(32)は言う。
「大学病院の手取りは月20万円台後半で、バイト代の方が多い。バイトは1回5万円、週に1回だから月に20万円。1カ所なくなるだけで、困ります」
医療ガバナンス研究所の上昌広理事長は言う。
「問題は個別の病院の過酷な労働環境です。特に大学病院は後期研修医を時給1300円程度で囲いこんでおり、課題が多い」
医師の就労環境は特殊だ。一部の医師は過労死ライン2倍の残業が認められている。地域医療の確保のために必要な医療機関の医師、また初期・後期研修医に限り、年間1860時間の時間外・休日労働が認められる。




































