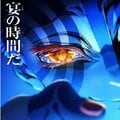東京一極集中により地方への関心は薄れ、里山では過疎化が進み続けています。
「都市化、それは世界の傾向であり、否応なく各国で進行している。では、農山村に人が住まなくて良いのか。筆者は、我が国には、これに追随するわけにはいかない決定的な理由があると考えている」
とは、書籍『ソーシャルアートラボ:地域と社会をひらく』に寄稿した九州大学大学院芸術工学研究院准教授・朝廣和夫さんの言葉です。朝廣さんは里地・里山の保全、都市緑地の保全等をキーワードに教育研究を推進。また、各地の災害で農業支援・農地等復旧ボランティアの実装支援を展開しています。
さて、先述した「決定的な理由」とはなんなのでしょうか? それは「温暖多雨な気候と急峻(きゅうしゅん)な地形である」と朝廣さん。「この国で暮らし続けるには、里地・里山を管理しつづけて時折来襲する災害に対応し速やかな復興をしなければならない」という。
そのためには過疎化を食い止め、里地・里山へ人々の関心を向ける必要があります。朝廣さんは「里地・里山保全活動の延長線上に、アーティストによる農山村の価値の言語化と表現活動の可能性を考えている」と記します。
「都市生活では見えない価値を、アーティストがさまざまな関与者(ステークホルダー)と共働しながら、統合し、表現する。そして、その価値をより強く、広く、遠くへと伝える。そのようなアートは、関与者と農山村のつながりに新たな方向性や、仕組みをももたらすことができるだろう」(同書より)
またアートは、自然災害などの大きな恐怖に寄り添ってきた側面があります。
「自然災害は、往々にして『昨日とつながらない今日』を生きることを私たちに強いる(中略)このような時代の雰囲気によるものか、漫画やアニメーションの世界では『ループもの』(時間を巻き戻して現実をやり直す)というプロットがよくみられるようになった」(同書より)
上記は、九州大学院芸術工学研究院教授・知足美加子さんの言葉。木や鉄等の実在を使った彫刻作品の制作研究のほか、震災支援「福岡エルフの木」「ちいさいおうち(板倉小屋プロジェクト)」、九州北部豪雨「災害流木再生プロジェクト」などの活動をしている人物です。
九州北部豪雨「災害流木再生プロジェクト」では、知足さんが樹齢132年の樟(くす)の流木の彫刻を被災地の小学校に寄贈しています。そこには以下のような思いが込められていました。
「さまざまな困難を記憶している木を、創造の力によって子どもたちをエンパワーするものとして再生したい。子どもたちが地域を好きでい続けてくれれば、未来はあるのではないか」(同書より)
日本に住む人々にとって、もっとも身近な災害である地震。直近では能登半島地震が2024年1月1日に発生しました。それから約4カ月が経ち、被災地は少しずつ日常を取り戻しつつありますが、被害の大きい場所はまだまだ時間がかかりそうです。被災した人々は今も"昨日とつながらない今日"を懸命に生きています。
夏の始まりを告げる「あばれ祭」などで知られる酒垂神社は、樹齢200年超の御神木が地震による土砂崩れで倒木するなど大きな被害を受けました。現在、神社の再建と地域復興を目指してクラウドファンディングを実施中です。
「倒れた御神木を神社の再建と能登の復興のシンボルとして活用したい」との想いから、御神木から作られた復興祈願絵馬やノンアルコールの無糖飲料「木のソーダ 御神木 杉」を返礼品にしています。
同書では他にも、「ソーシャルアートラボ」(=社会とアートの関わりをとらえなおす実験の場)に関わる研究者、アーティスト、実践家たちが、自らの試行錯誤や実践をメタ的な視点から語っています。アートが社会にどのような影響を与えているのか、この機会に潜考してみてはいかがでしょうか。
[文・春夏冬つかさ]