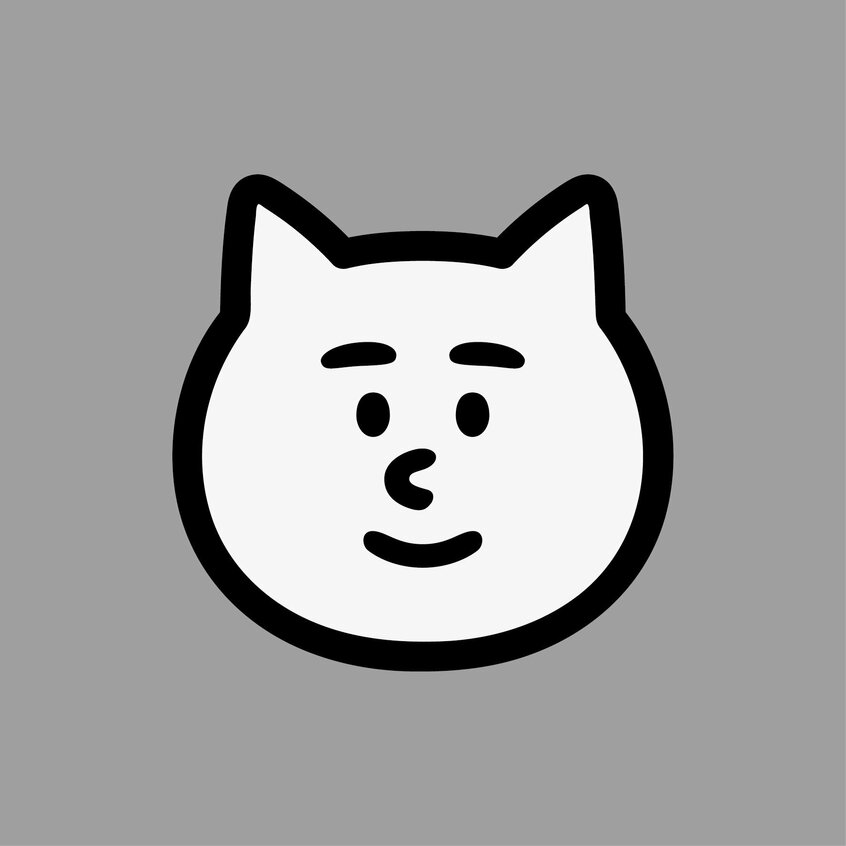
『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』などで知られる小説家・麻布競馬場さんに、おすすめの本と書店の思い出を聞いた。AERA 2024年4月29日-5月6日合併号より。
* * *
先日、新刊『令和元年の人生ゲーム』を出しました。その原点となるような3冊を紹介します。
最初の作品は大江健三郎『死者の奢り・飼育』に収録されている「他人の足」。この作品を初めて読んだのは中学生のときでした。学校で読む教科書が正しく清らかな心を持つ人間を賛美していたあの頃、そうなれない僕は疎外感を抱えていました。そんななか、憧れを孕んだ妬みや軽蔑がリアルに描かれているこの物語にどこか救われた気がしたんです。文学とは善き存在としての人間を喧伝するだけじゃない。絶対的な正しさを強制される時代に、正しくない自分がどうあるかを考えるのも文学なんだ。そう教えてくれたこの作品の現代版を、僕は書き継いでいる気がします。
2冊目はマイケル・オンダーチェ『イギリス人の患者』です。この本はまず原書で読み、圧倒されました。戦争が終わる直前のイタリア。廃墟となったある屋敷で、傷を抱えた4人が共同生活をする。そのことを綴った小説はじつに多様な読み方を誘います。大きな歴史と個人の軋轢、愛の暴力性、所有できないものを所有しようとすることの虚しさと美しさ。読むたびに自分の内面が反映されて、異なる解釈をしたくなる。小説の持つそんな力に驚かされました。原書を読んでから日本語版も読んだのですが、土屋政雄さんの翻訳がまた素晴らしいんです。脳にすぐ届く単純さだけではなく、人間の複雑さを緻密に描くことの意義を教えてくれた一冊です。
文学が生活描く意味
最後に紹介するのは辺見庸『もの食う人びと』。これは辺見庸が諸国をめぐり、食を通じて文化や歴史を理解するルポです。なかでもポーランドのヤルゼルスキ元大統領を訪ねる一篇は忘れられません。肉なしの質素な食生活でもやっていけると語る元大統領。その発言の裏には資本主義への批判があるのですが、最後、じつは最近、ワッフルを食べるようになったと告白するんです。その瞬間、強さを誇示してきた男の隠しきれない弱さが垣間見える。文学が生活を描くことの最大の意味がここには込められていて、今、僕が書いているものに繋がっている作品です。
以上が原点となる3冊ですが、僕をかたち作った書店に、今は無き渋谷のMARUZEN&ジュンク堂書店があります。大学や仕事の帰りに寄っては本を買い、飲み屋へ向かってました。書店は自分が気づかなかった欲望を気づかせてくれる空間なんですよね。それは図書館も同じ。僕は古い知に触れるのが好きなので、図書館もよく行きます。昔、広尾の都立中央図書館で夏目漱石を全部読むという企画を一人で立ち上げ、完遂したことがありました。そんなことができるのも図書館のパワーですね。
(構成/ライター・長瀬海)



































