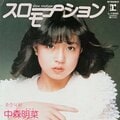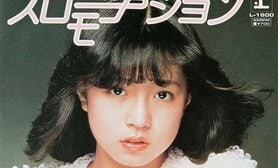SASの治療には、睡眠中に舌がのどに落ち込まないようにする専用のマウスピースを装着し、気道を確保する方法があります。重症の場合は、夜間に装置からエアチューブを伝い、鼻や口に装着したマスクから気道へと空気を送り込む「CPAP(シーパップ)療法」もあります。こうした治療によってSASの症状が緩和すれば、日中の精神状態や活動性も向上し、睡眠の質も向上します。
「SASのある認知症患者をCPAPで治療すると、認知症によって不安定な精神状態にあっても、それまでより穏やかになることが報告されています」(同)
昼間の活動性低下も睡眠の質を下げる要因に
高齢者世代の睡眠の質を妨げる要因には、「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」もあります。じっと座ったり横になったりすると、脚のむずむず感、痛み、かゆみなど、脚に不快な症状が表れるのが特徴です。
「高齢女性に多くみられる症状で、発症には鉄欠乏性貧血やドーパミンの機能低下なども関連していると考えられています。睡眠が妨げられ、生活に支障が出ている場合は薬で治療することもあります」(内村医師)
ほかの要因としては、昼間の活動性の低下もあります。睡眠の質を高めるためにも、昼間の外出や人との接触、日光を浴びることなど、積極的に外に出ることを心がけましょう。フレイル(加齢により心身が老い衰えた状態)などによって、外出がしにくい場合には、デイサービスやデイケアをうまく利用することで、これらの活動を確保できるケースもあります。
加齢によってからだや生活が変化することに伴い、睡眠のサイクルも変わるのは仕方のないことです。そのことを理解して、年代にあった適切な睡眠をとることが、認知症予防や健康維持にもつながります。
「まずは睡眠衛生の改善です。それでも不眠が改善せず、生活になんらかの支障が出ている場合は、病的な不眠や睡眠障害かもしれません。すべてが年齢によるものだと自己判断せずに、医療機関に相談しましょう」(安達医師)
(文/石川美香子)