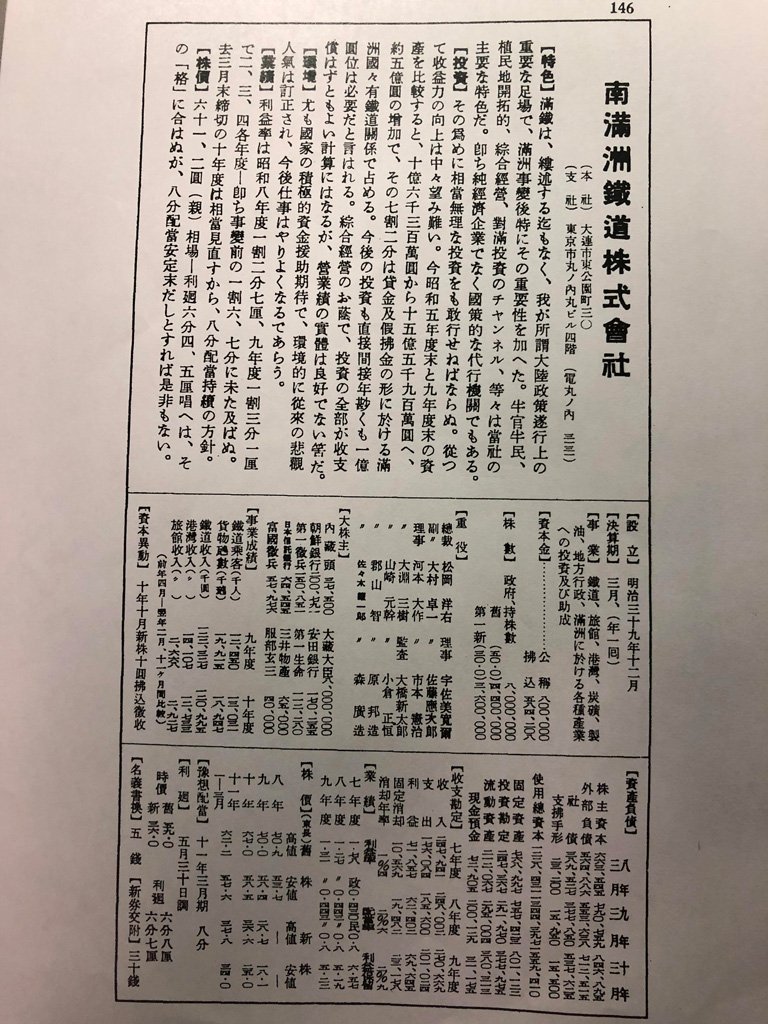
この記事をきっかけにファナックの株価は大幅に下がった。ファナックはあわてて、広報室を新設し取材対応をするようになった。それにたいして「四季報」の秋号では「改善」として広報室新設の事実を記した。
1979年3月に日本経済新聞が、『日経会社情報』という『会社四季報』のライバル商品をだした時、日経のデータバンク局長だった鈴木隆は、日経のデジタル化を背景にすれば、東洋経済新報社など敵ではないと、田原総一朗の取材に答えている。
「東洋経済さんの記者がひとつひとつ取材して書いているという、そういうものではなく、ウチは、全く自動的にできてしまう」(『電子戦争・メディア戦争』1983年 文藝春秋)
それに対して『会社四季報』が装備した新機軸は、2年先までの業績を記者が予測するという「2期予想」だった。
これは1982年に『会社四季報』の編集長になった篠原勲の時代に始まるが、篠原はこんな言葉を残している。
〈日経は新聞社、東洋経済は雑誌社、その違いは何かとも考えました。やはり新聞社は客観情報を重視しており、会社の発表した予想数字にこだわらざるをえないのではないか。一方、雑誌社は記者の取材、分析に基づいた独自予想という特徴が出せる〉(会社四季報全70年DVD 付録冊子より)
当時は日本にはまだアナリストという言葉すらなかった時代だった。篠原は、アメリカにはアナリストと呼ばれる人たちがいて、3期や5期先の予想をする情報誌があるという話を聞きつけ、足で企業をまわっている東洋経済新報社ならば、これができると考えた。
これは大ヒットとなった。『日経会社情報』には、会社が発表する一年先のみの決算予想はあるが、記者が独自に将来の決算を予想をするという欄はなかった。『日経会社情報』のシェアは3割を超えることはなく、『会社四季報』は常に7割のシェアを確保した。
現在、東洋経済新報社の売上115億8000万円のうちデジタルからの収入は5割を超えている。そのうちの大きな売り上げを占めるのが、四季報で集めたデータをBtoBで機関投資家に売るバルク販売だ。なかでも、2期予想は、海外の機関投資家も購入する人気商品だ。
『日経会社情報』は2017年春の号を最後に紙の市場からは撤退する。ダビデはゴリアテに勝ったのである。
現在編集長をつとめる冨岡耕(こう)は、2007年に産経新聞から移ってきた。

































