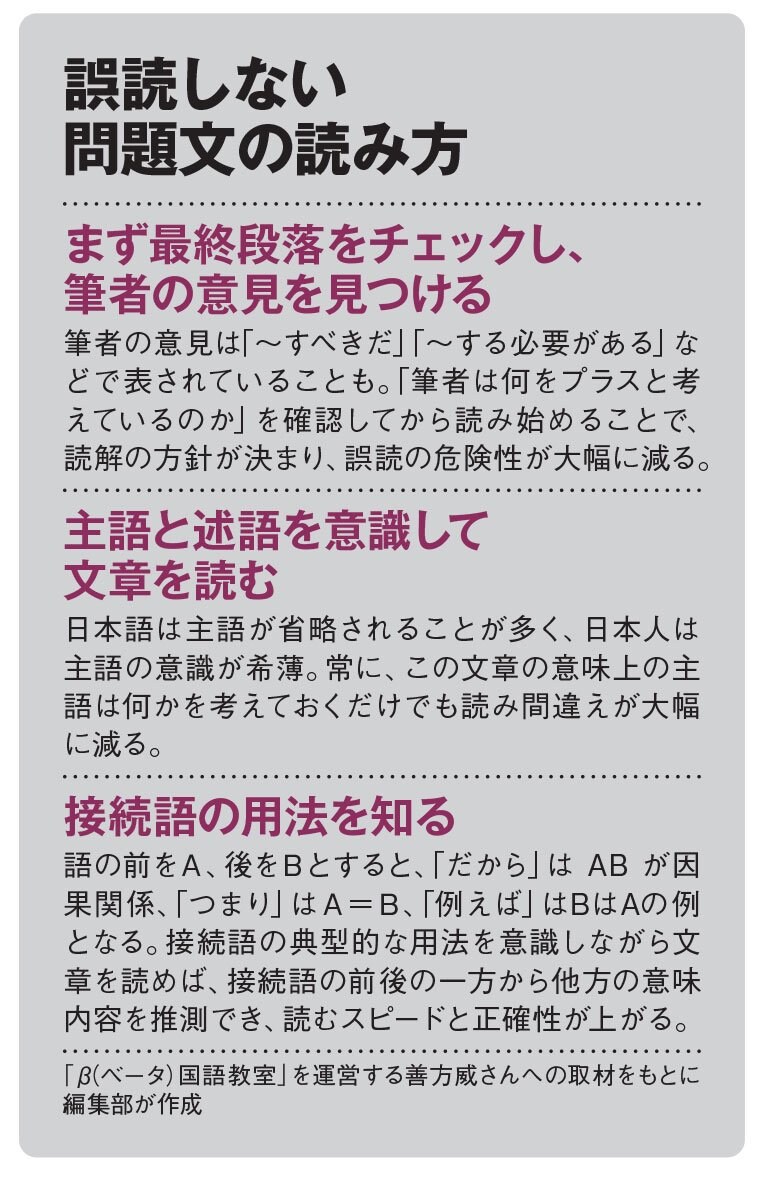
「読解力と一言でいっても、学校側の要求する内容やレベルには違いがあります。合格のためには志望校がどのような読解力を求めているかを理解し、対策をすることが必要です。しかし、それができている受験生は少数。塾の模試や入塾テストでは長い問題文が使われるため、それが当たり前だと勘違いしているのです」(善方さん)
百害あって一利なし
親が目にする問題文が長いことから、多くの保護者は「長い文章を読む力は必須」と思うようになる。そのために塾に行かなければ、と思いこむ保護者も出てくる。結果的に、受験生は長すぎる問題文を前提に、練習を重ねることになる。
そのための弊害も生まれている。試験には時間制限があるため、読み切ることができない子は飛ばし読みをしてしまう。長すぎる問題文に対応させるために「傍線部分にジャンプして読め」と指導する家庭教師や塾講師もいる。そうでもしないと、読み終わらない試験があるのも事実だ。だが、
「飛ばし読みは、特に中堅校狙いの子には百害あって一利なし。その読み方が習い性になってしまい、『文章って、飛ばし読みするものだ』と思うようになる。すると、当たり前に誤読をするようになります」(善方さん)
本来であれば、まず短い文章の精読ができなければならないが、長い文をざっと読む訓練を重ねているのが現代の中学受験生なのだ。
問題を出す学校側はどう考えているのか。都内のある男子校は、「特に意識して長い文を出題しているわけではない」と、明確な意図はないとしている。それを受けて善方さんは言う。
「インターネットで誰もが情報を発信できるようになり、世の中の情報量は爆発的に増えました。そのような中、問題をつくる先生方の潜在的な意識として、文章が長いことに対する抵抗感が薄れてきたのだと思います。『長い文を速く読むことは当たり前』と感じている人が、増えているのではないでしょうか」
(ライター・黒坂真由子)
※AERA 2023年8月7日号より抜粋








































