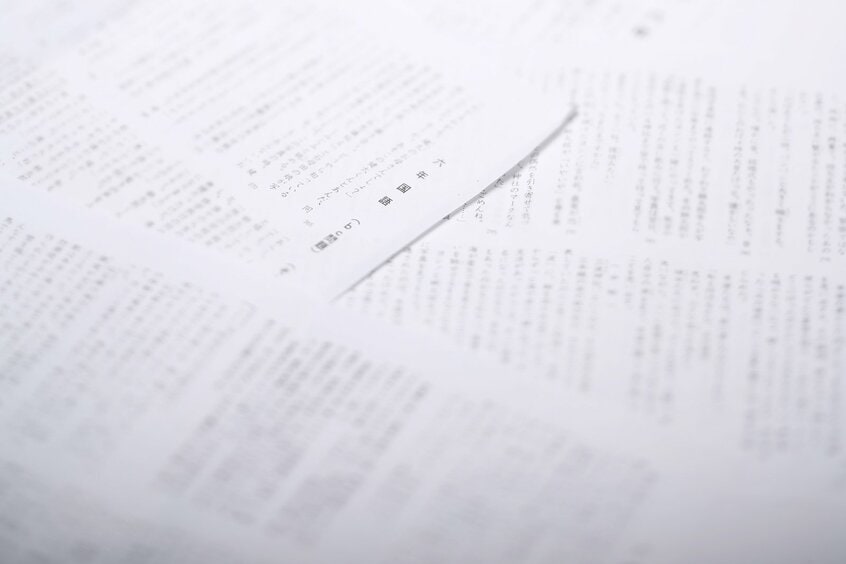
中学入試の国語では問題文が長すぎて全部解き終わらない子どもが続出している。読解力をつけるどころか飛ばし読みも横行し、誤読が頻発して本末転倒の事態となっているという。AERA 2023年8月7日号の記事を紹介する。
* * *
丸つけをするだけ。そう思っていたが、甘かった。
息子の中学受験を来年に控え、都内在住の40代女性の日課には過去問の丸つけが加わった。ミスが多いのは、国語の長文問題。論説文と物語文が出題されるが、どちらも半分合っていればいい方だ。なぜ間違ったのかを子どもに説明するためには、自分も問題文を読む必要がある。しかし、この問題文がおそろしく長い。選択肢まで長いのだ。その日、丸つけをした国語の過去問のページ数は、全22ページ。とても夕飯後にこなせる分量ではない。
中学受験では、多くの学校が長文を2題出題する。1題は論説文。もう1題は物語文だ。例えば開成中学で今年度出題された文章を見ると、1題目の論説文は隈研吾著『ひとの住処』、2題目の物語文は柚木麻子著の『終点のあの子』。当たり前のように大人が読む本から問題文が引用されるため、小学6年生の子どもにとっては難易度が高い。さらにそれが長文となると、そもそも時間内に読み切ることができない児童も出てくる。
原稿用紙50ページ分も
このような状況を、専門家はどう見ているのだろうか。
都内で長年、「β(ベータ)国語教室」を運営し、『全教科対応! 読める・わかる・解ける超読解力』の著書もある善方威さんは「実際には、問題文の長さは学校によってばらつきがある」と言う。
例えば、2023年度の開成中学は50分で合計1万2千字ほどの問題文を読む。原稿用紙で30ページ分だ。漢字を除いた問題数は合計7問。すべて記述式だ。同校を受ける児童が第2、第3志望として選ぶある男子校は、選択肢問題が中心の問題構成で、60分で約1万5千字の問題文と約5千字の選択肢を読まねばならない。原稿用紙に換算すると50ページ分だ。このように、あまりに読む量が多すぎて、もはや「御三家」の滑り止めに適さなくなった学校も出てきているという。
「中学受験において、各学校が子どもに求める国語力には大きな違いがある」と善方さんは言う。開成などのトップ校では、問題文はそれほど長くはないが、精密な読み取りが求められる。設問の実質的な意味内容を理解することも簡単ではない。何が問われているのか、どう答えればいいのか、悩む問いも多い。
一方で長い問題文や選択肢を出題するいくつかの上位校は、「大量の情報をそれなりに処理する能力」を求めている。問題文の量は多くても設問自体は平易なため、さっと読んで、さっと解答できる子が良い点を取ることができる。




































