
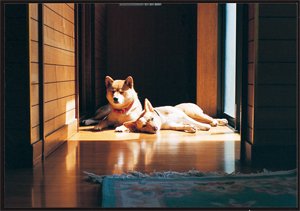

――実家が写真館だそうですね。
そうなんです。小学校高学年になると、おやじに暗室へ連れていかれて、現像まわりのことをあれこれ教わりましたよ。ぼくを写真屋にしたがっていたんです。兄がいるんですが、「上の子は大学に行かせる。おまえは勉強もイマイチだから、写真屋をやらせよう」というわけ(笑)。ところが、ぼくは写真がうまく撮れない。学校で行事があるたびにカメラを渡されて撮らされたんですが、ピンボケばかり。シャッターを押すと一緒に体も下がる癖があったんです(笑)。「写真屋の息子がこんな写真を撮ってどうする」とおやじにしょっちゅう怒られた。だからぼくは、写真屋にだけはならないと徹底的に抵抗しました。だけど噺家になったあと、師匠(六代目三遊亭圓生)とけんかして、「もう落語家をやめよう」と実家に戻ったことがあったんです。するとおやじが「いい機会だから、写真をやれ」と言い出したんで驚きましたよ。「それだけは絶対に嫌だ!」と、今度は実家を飛び出して東京に戻った(笑)。「すみませんでした」と、師匠に頭を下げて噺家に戻ったんです。
――ご自分でカメラを持ったのは、ずいぶん後のことですね。
狛犬に興味をもったのがきっかけだから、1990年代の初めくらいです。世間では狛犬なんかどれも同じだと思われてますが、地域によって特色があったり、表情も一つひとつ違っていて、とても興味深いんです。なんともいえない恨めしそうな顔をしているやつを見て可哀想になって、家に引き取りたいと真剣に考えたこともあります。そんな狛犬との出合いの感動を写真で残したいと思うようになった。最初は形のめずらしい狛犬を見つけるのが面白かったんですが、最近は名工といわれる石工の彫ったものに興味が移ってきた。名人の狛犬は見た瞬間、はっと息が止まるような迫力がある。100年、200年と時を超えて、石工と話をしているような気持ちになるんです。
――狛犬撮影のポイントは?
ぼくは何でも単純化して考えるほうなんです。新作落語をつくるときも、どこを切り取るのかって突き詰めていって、必要ないものはどんどん削ってしまう。狛犬もそれと同じでアンダー気味にとらえ、バックは必ずボカして、「狛犬のブロマイド」を撮る感覚でやっています。天気は曇りや雨がいい。石は色がついてないからカンカン照りだと、セメントみたいにベタッとした感じになっちゃう。石そのものの質感、存在感が出るのは光が少ない悪条件のときです。ただ、そのコツをつかむまでには時間がかかった。
カメラにまったくこだわりがないから、最初はコンパクトカメラを使っていました。でもバックはボカせないし、ファインダーからのぞいた画とできあがったものに微妙な誤差が出る。それが許せなくてもう1台、別の機種を買ってみたけど、それもダメ。やっぱりコンパクトカメラには限界があると気づいて、半年くらいでペンタックスの一眼レフに買い替えた。これにいちばん明るいレンズをつけてやっと納得のいくものが撮れるようになりました。フィルム千本くらいは撮りましたね。
――今はオリンパスE-510ですね。
5年くらい前、秋葉原の量販店で買ったものです。一眼レフのデジカメの中では比較的安く、小さくて使いやすそうだった。でも、デジタルは機能を増やしたぶん、使いづらくなっている気がするね。シロウトが撮るものに、そんなに高機能なものが必要なのかね。それに、写真の管理もわずらわしくなった。だからつい放置して、たまる一方になっちゃう。ほんとうに残したいものは最終的には、狛犬みたいに「石に刻む」のがいちばんかもしれないね。
※このインタビューは「アサヒカメラ 2012年3月号」に掲載されたものです

































