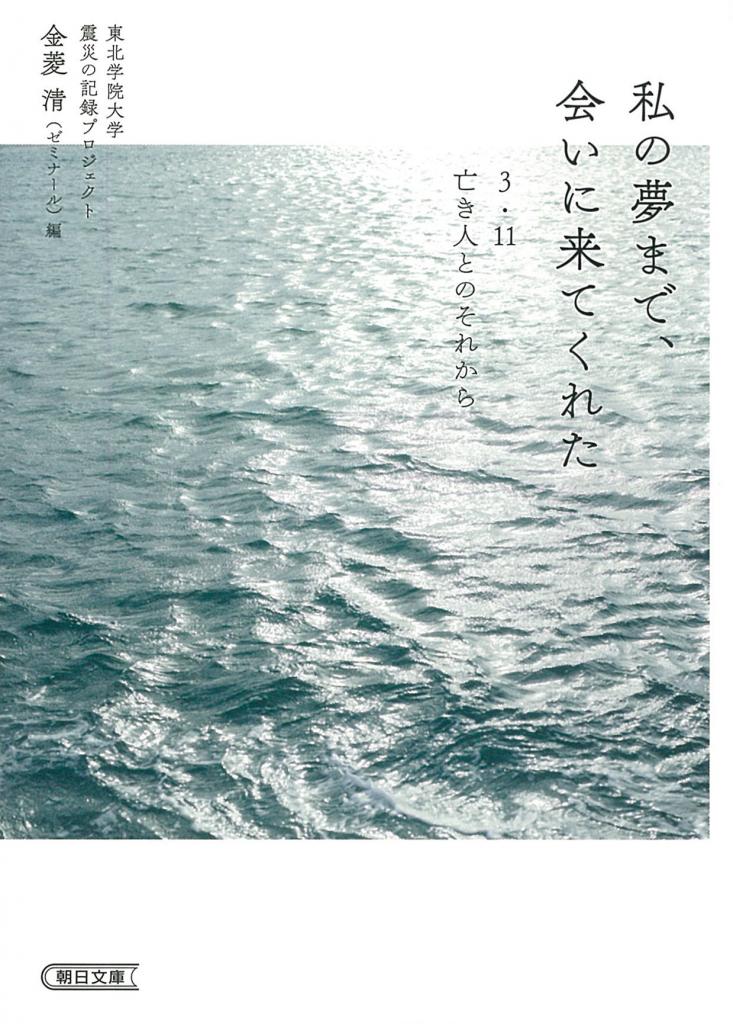
金菱:『荒地の家族』も祐治という、たった一人の生活しか描いていませんし、震災には深く触れていません。だからこそ、その人にとって、いかにものすごく大きな出来事だったのかが伝わってきます。
佐藤:祐治は前に進もうと頑張るんですけど、堂々巡りをしてしまう。災害や大病を経験した人も祐治のように元に戻したくて頑張るんだけど、思うようにいかないことがたくさんあると思います。もがくなかで、日常にしがみつこうとするのは、誰にとっても特別なことではない気がします。
金菱:祐治が中年の男性で植木職人というのもリアルに感じました。被災地では「お茶っこ飲み会」みたいな集まりがよく開かれたんです。お茶を飲みながらおしゃべりすることで、少しずつ日常の落ち着きを取り戻すという。だけど、参加するのは女性ばかり。男性は「しゃらくせぇ」って出てこない。気にはなるんだけど、一人で酒を飲んで時間を潰すようなことが珍しくありませんでした。祐治が仕事をしながら、心のなかでぶつぶつとつぶやく姿には、被災地で見かけた中高年男性の姿が重なります。
佐藤:直接的な原因でなくても、震災が何かしらの不調や怪我(けが)の治りにくさなど、フィジカルにもメンタルにも傷を与えていることは、多いのではないでしょうか。
金菱さんに伺いたいのですが、研究の対象となる相手にアプローチするとき、どんなところに難しさを感じますか。
金菱:社会学は仮設住宅や避難所など、範囲を決め、集合的に考察することは得意です。でも、従来の方法では漏れてしまうことが山ほどある。それをどう拾うか、いつも模索しています。
震災後に初めて編纂した『3・11慟哭(どうこく)の記録』では、当事者が見たまま、感じたまま、震災に遭遇した様子を手記として書いてもらいました。その後、幽霊や夢についてインタビューしたり、亡き人に向けて手紙を書いてもらったり、テーマや手法が深まっています。とくに手紙を書いてもらったときは、聞き書きでは絶対に出てこない想いを綴られていたことがショックでした。インタビューという手法が、いかに聞く側が何かを設定した上で聞いているのか、理解したいことだけを聞いているのか、と反省させられたのです。




































