■ここ10年で次々に新薬が登場。治療の選択肢はさらに広がる
そして、現在もっとも進歩しているのは薬物療法です。
「がんが大きくて切除できない場合や、ほかの臓器への転移がある場合でも、近年承認された分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を使ってがんを小さくし、手術ができるようになるケースが増えてきました。分子標的薬と塞栓療法との組み合わせ治療でも効果が見られています」(阪本医師)
肝がん治療の選択肢の中で、海外と比べて極端に少ないのが肝移植です。阪本医師はその必要性についてこう話します。
「日本では、近親者から肝臓の一部を譲り受ける生体肝移植が中心です。脳死のドナーによる脳死肝移植の場合、肝移植全体の17%(2020年)にすぎません。肝がんに対する脳死移植の適応も、肝機能が低下した肝硬変の患者さんに限定されています。
しかし、肝移植後の10年生存率は71%。肝切除の44%に対して27%も高いのです。若くして発症した患者さんの場合は特に、肝移植は重要な選択肢となります。日本は肝切除の技術が高い国ではありますが、肝移植という選択肢を忘れてはいけないと思います」
■肝がんこそ、セカンドオピニオンがおすすめ。納得して治療を!
さまざまな治療法があるものの、基本的には日本肝臓学会のガイドラインに沿って治療法は決められていくことが多いもの。「できるだけからだに負担の少ないアブレーション治療をしたい」と思っても、がんが大きい場合や数が多い場合、治療を受けられないケースもあります。失望する患者も多いですが、「その人に合う治療法を提案するのが医師の仕事」と前出の土谷医師は言います。
「肝がんは治療の選択肢が多く、組み合わせも可能です。私自身は『残念ながらアブレーションはできません』ではなく、『あなたのがんに向く治療法は、アブレーションではなく、もっと適したものがあります』という表現を心がけています。医師は患者に対して、治療の難易度、合併症の有無、必要であれば代替治療案も提案することが必要です」
医師に質問しても納得できない場合にはどうすればいいのでしょうか。
「納得できない場合はもちろん、納得していてもセカンドオピニオンを受けてほしいと思います。主治医以外の医師から丁寧な説明を受け、満足して治療を受けることはとても重要です」(土谷医師)
(文・神 素子)
【取材した医師】
武蔵野赤十字病院 消化器科部長 土谷 薫 医師
杏林大学病院 肝胆膵外科診療科長 阪本良弘 医師

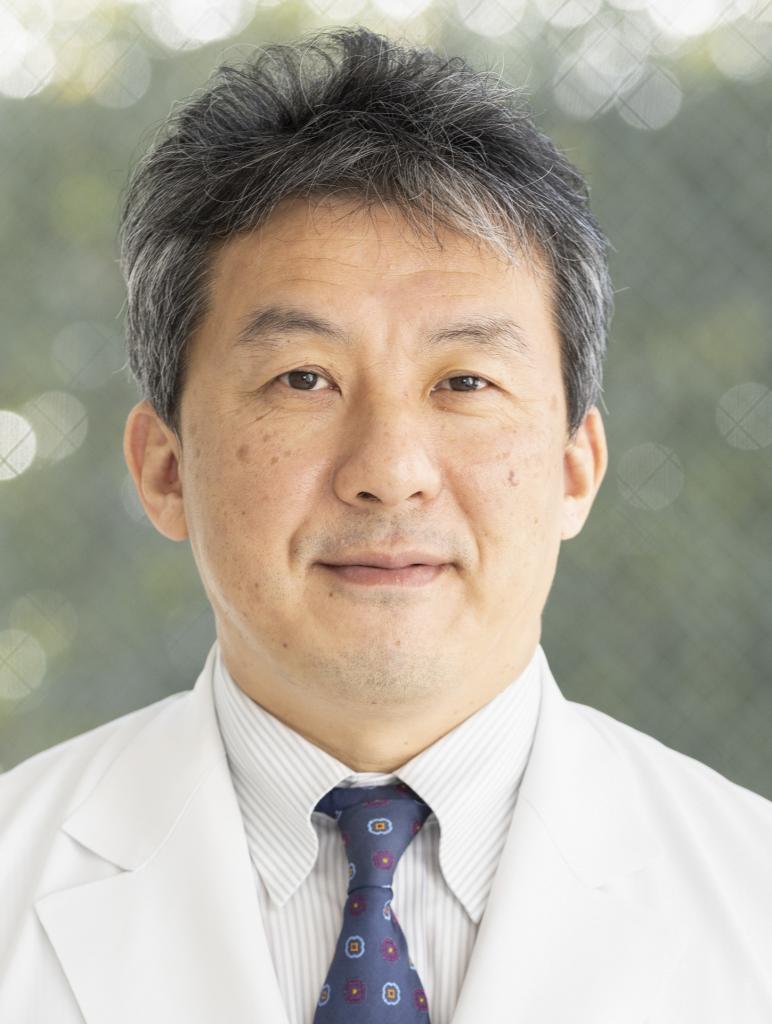
「肝がん」についての詳しい治療法や医療機関の選び方、治療件数の多い医療機関のデータについては、2023年2月27日発売の週刊朝日ムック『手術数でわかる いい病院2023』をご覧ください。







































