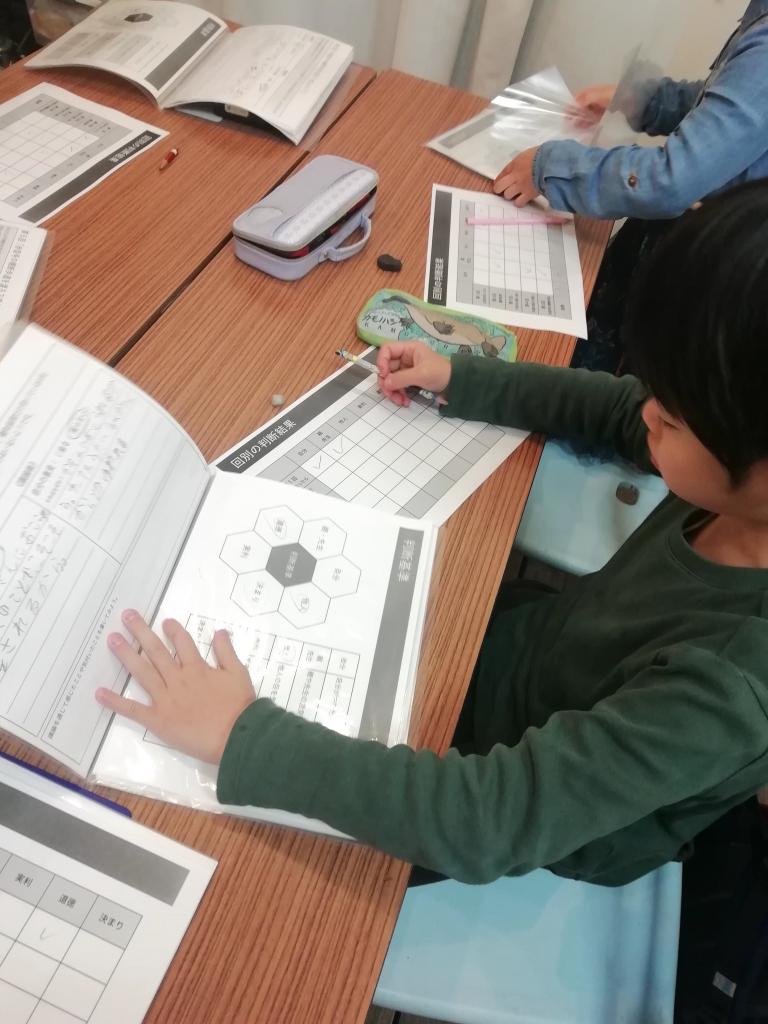
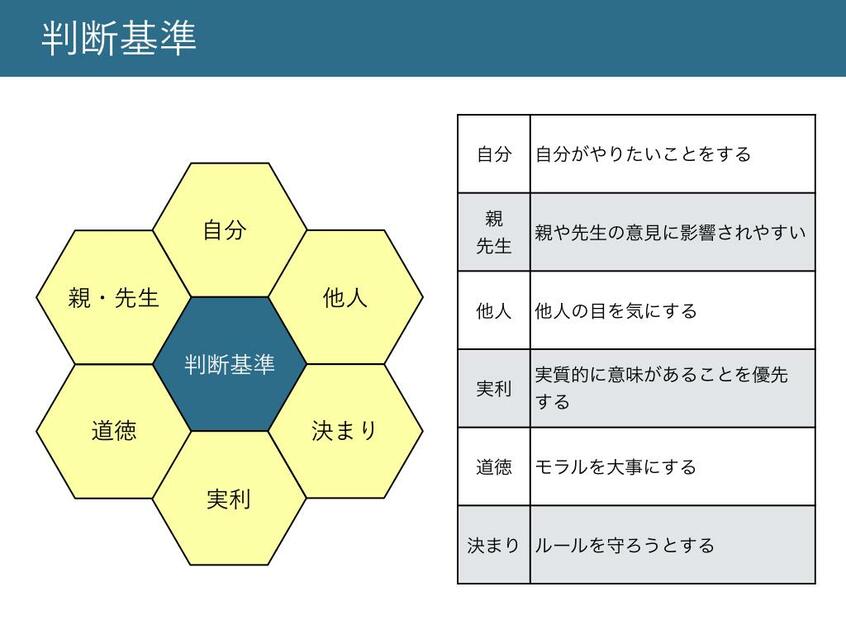
たくらみ中学年(小学3・4年生)クラスでは現在、「選択」をテーマにしたプロジェクトに取り組み中です。
「人生は選択の連続である」を合言葉に、議論を通じて、身近な「答えのない問い」について考え続けています。
今回のお題は「やるべきことがある中で、友達の遊びの誘いを断る?断らない?」です。
週末に宿題をたくさん抱えるなかで、友達から魅力的な遊びのお誘いがあった場合に、あなたならどちらを優先するのかという内容で子どもたちに問いかけます。
「うーん、悩むなぁ……」
ワークシートに議論前の自分の意見を書く際に思わず独り言がこぼれます。
彼らにとって、これまでのお題の中で最も現実味がある状況なのかもしれません。
ワークシートが書き終わったのを見計らい、どちらの立場を取るか確認しました。
結果はクラス4人中3人が「断る」を選び、「断らない」を選んだのは小3のAくん1人だけでした。
(ほぉ、友達と遊ぶのが大好きな最上級生のKくんは「断らない」の方を選ぶかと思ったんだけどな。)
まずは多数派の意見を聞いてみることに。
「宿題忘れで先生に叱られたくないわ」
「家に電話されて、お父さんやお母さんから怒られたら最悪やし」
「僕やったら、先に宿題を終わらせちゃうかな。また次の機会に遊べばいいやん」
結論は同じでも、その背景にある考えの違いが見えてくるのが議論の面白いところです。
「なんとか時間を作って遊ぶ! 例えば、朝早起きして宿題を片付けるとか」
ひとり「断らない」と論陣を張る男の子はどうしても遊びを優先したいそうです。
そこまでこだわる理由がふと気になり、さらに深掘りして聞いてみます。すると、彼の学校の休み時間への不満が浮き彫りになってきました。
彼いわく、休み時間とは名ばかりで、実際には授業の課題などでつぶれてしまうことが多いとのこと。
現場の事情を把握しているわけではありませんし、担任の先生の言い分もあるでしょう。ただ、私はこの発言を聞いて、何とも言えない複雑な気持ちになりました。
「実は先週も宿題忘れをしていたとしたらどうする?」
「クラスメートも一緒に参加すると言ったら?」
追加条件を次々に提示し、子どもたちの考えに揺さぶりをかけます。





































