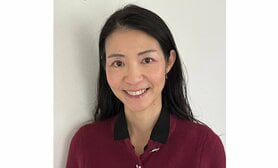幕末、明治、戦国、宗教、この国のかたち。歴史が交差する瞬間をカメラマンはどう表現したか。司馬遼太郎さんの小説やエッセーなどの世界を文章と写真で表現する連載を担当するカメラマンが、その苦労などを明かす。AERA 2019年11月4日号に掲載された記事を紹介する。
* * *
司馬遼太郎さんが「週刊朝日」に1971(昭和46)年から25年間連載した「街道をゆく」。紀行文や文明論でもあり、小説的な要素もある。
自作を“絵画的”に司馬さんは語っている。
<……初めのうちは旅行印象記といいますか、淡い日本画みたいなものだったんですが、次第に油絵になってゆき、アブストラクトやシュールじみてきたわけで、書き続けるうち、その土地ならその土地で、自分が感じている大テーマを書こうと……>(『司馬遼太郎全集』月報50)
中盤以降は「南蛮のみち」「愛蘭土(アイルランド)紀行」「北のまほろば」「台湾紀行」といった大作が多くなる。
文庫本43冊は司馬さんのライフワークだろう。司馬さんはかつて言っていた。
「人間のアプローチの仕方にはいろいろあって、絵画的に入る人、音感的に入る人、触感で入る人、味覚で入る人もいる。僕の場合は視覚的に入るタイプだろうね」
取材でスケッチし、メモ代わりに写真もよく撮っていた。
こうした司馬さんの「街道の視点」に視覚的に“挑戦”したのが、写真集『司馬遼太郎「街道をゆく」の視点』だ。
司馬さんの没後10年から週刊朝日で連載が始まった「司馬遼太郎シリーズ」はいまも続いている。小説やエッセー、「街道」の世界を文章と写真で表現する連載(現在は「司馬遼太郎と昭和」)で、編集担当は筆者と朝日新聞出版写真部の小林修。小林は13年にわたり写真を撮り続けてきた。
小林の朝日新聞入社が1990(平成2)年で、司馬さんが亡くなったのは96年。まだ駆け出しの時期で、「街道」チームに参加したことはない。つまり、小林は司馬さん本人に会ったことはない。もともと小説もあまり読んではいなかった。