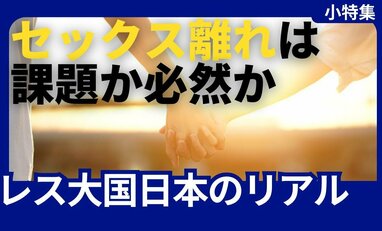夏の風物詩だった怪談、ホラー映画は、今や通年楽しめるエンタメだ。100年周期といわれるホラーブームの陰には思わぬ効用もあるようだ。
深夜。東京・六本木のロアビルに、女性の悲鳴が響きわたる。今年5月にオープンした「スリラーナイト六本木」には、怖いもの好きな客たちが、夜な夜な集まってくる。1時間に一度、「怪談師」が登場し、怪談を語る。悲鳴の主である女性客は、普段はネットで怖い話を探して読んでいるという。
「怖さと高揚感や楽しさって紙一重。日常的に怪談が聞ける場がもっと増えたらうれしい」
今、文学から映像までさまざまな「恐怖するというエンターテインメント」が楽しまれている。
不思議や神秘、心霊をテーマにしたコミック誌「HONKOWA」(朝日新聞出版)の主な読者も女性たちだ。1991年の創刊(当時は「ほんとにあった怖い話」)から根強い人気がある。年齢層も広がりを見せる。
「本気で子どもを怖がらせる本があってもいいのではないか」と2011年に発刊されたのが、東さんが監修を務める岩崎書店の怪談えほんシリーズだ。執筆陣には宮部みゆき、恩田陸などが名を連ねる。
子どもに怖い思いをさせるのはよくない、と過保護な自主規制がかかっていた時期もあったが、そんな認識は改まりつつあるという。情操教育によいとされ、子ども向けの読み聞かせの題材としても使われる。
「想像力の欠如が引き起こす問題が現代には多い。想像力を働かせること、恐ろしさと面と向かうことは子どもにとって大事な体験なんです」(東さん)
テレビシリーズ「ほんとにあった怖い話」監督の鶴田法男さんは、Jホラーの父と呼ばれ、映像分野での第一人者だ。
「恐怖心があるからこそ、セーフティーが働き安全に生きていける。予想だにしないことが起きたときの対応をシミュレーションできるから、恐怖心を磨くことにはメリットがあるんです」
※AERA 2014年10月6日号より抜粋




![HONKOWA (ホンコワ) 2014年 11月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61OiV1PBhPL._SL500_.jpg)