
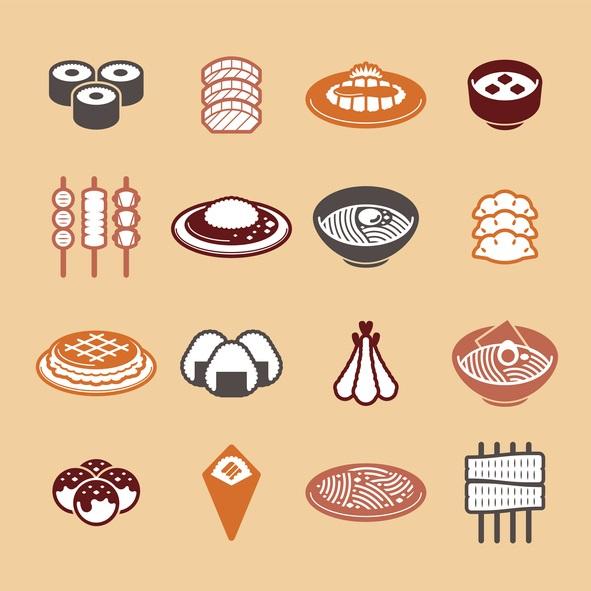
ギャンブル好きで知られる直木賞作家・黒川博行氏の連載『出たとこ勝負』。今回は1週間の出来事について。
* * *
夕方、よめはんが仕事部屋に来た。マフラーを巻き、コートをはおっている。
「なにしてんの」
「お原稿を書いてます」
「どれどれ」よめはんはパソコンを覗(のぞ)き込んで、「この○○いうひと、知ってるわ」
「刑事や。京橋署の」
○○は某小説誌に連載している警察小説の主人公だ。
「いま、被疑者の死体が発見されて、○○が臨場した場面なんや」
「被疑者の死因は」
よめはんは“被疑者”や“死因”といった専門用語を使う。わたしの影響だ。
「青酸化合物」
「ということは、これから青酸カリの入手先を捜査するんやね」
「いまどき、青酸カリウムいうのはないな。日本で製造されてるのは、ほとんどが青酸ナトリウム。青酸ソーダともいう」
「また、そうやって知ったかぶりするわ」
「ハニャコちゃんが訊(き)くからやないか」
「“後妻業”事件で使われたんも青酸ソーダなん?」
「そういうことや」
わたしはあの事件の裁判で判決言い渡しの傍聴にも行った。被告は小柄なおばあさん(逮捕時よりずいぶん老けて見えたのは、髪が白かったから)だった。
「で、ご用はなんですか」
「ごはん食べやんか」
「なに食うんや」
「ピヨコちゃんの食べたいもん」
「んなもんはない」いうだけ無駄だ。
「じゃ、お鮨(すし)かな」
よめはんがわたしに要求を訊くのは単なる形式であり、もしわたしが蕎麦(そば)を食べたいといっても言下に却下される。そう、よめはんは鮨を食うと、端(はな)から決めているのだ。
そんなことで、週に二、三回、わたしはよめはんに引率されて外食をする。行く店は、鮨、蕎麦、うどん、中華、お好み焼、ステーキハウスと決まっていて、それを順繰りにまわしていく(ファミレス、回転鮨などの外食チェーン店は行かない。みんな地元の店だ)。
うどん屋に行った。その店は鮨も出す。よめはんはメニューをためつすがめつして、『上にぎり御膳』と赤だし、わたしは定番のカレーうどんを注文した。


































