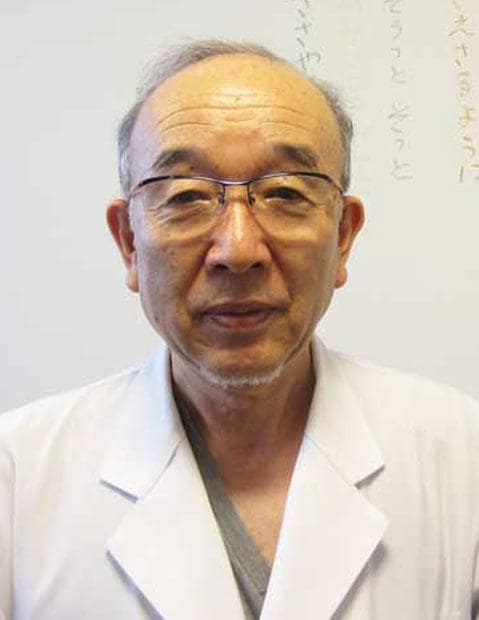
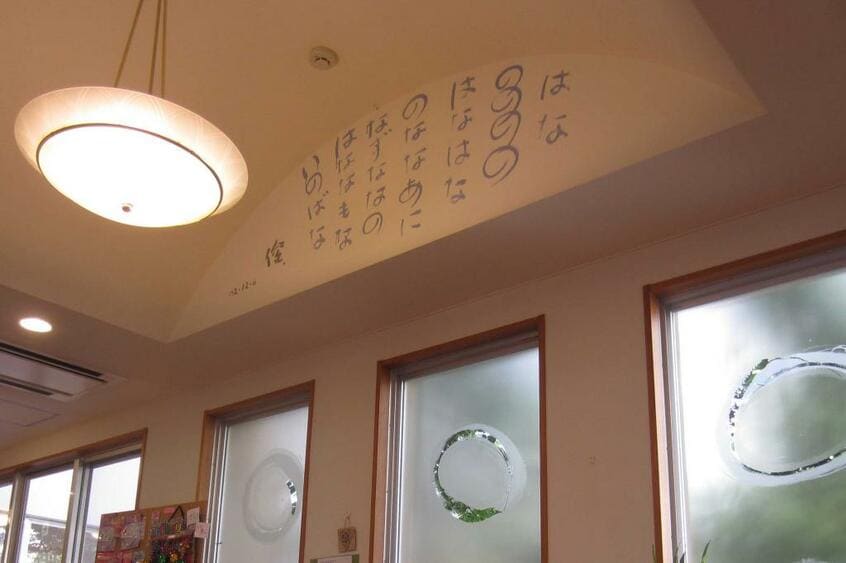
2001年、鳥取市に終末医療の拠点「野の花診療所」を開業した徳永進院長。この18年で多くの最後を見つめてきた徳永院長は、「頭が下がります、死に。死に向かっている人に、死を遂げた人に」と話す。私たちは先に逝く人々や自らに訪れる死と、どう向き合えばいいのでしょうか?
* * *
「死はいつごろになりますか?」
末期がんの患者さんの家族から、時には患者さん自身から聞かれます。医療者用のマニュアルに「年単位でしょうか」「月単位と考えてください」「週単位となったと思いましょう」「数日単位かと」「一~両日までのようです」と言うことなどと記されています。
身体の中の宇宙を透視するのはなかなか難しい。身体には思いがけないことが起こっています。急変、という言葉を使うことも多い。誰もが長い自分の命には長い時間が残っていると思いがちですが、実際は相当の割合で短く終わります。死の到来の兆候は血圧が下がる、手首の動脈が触れない、尿がでなくなる、呼吸を下の顎を使ってするなど。鼻の先の温度(鼻尖温度)が下がって冷たくなるのも大切な兆候です。
臨床は例外の宝庫。下顎呼吸が始まり、死は近いと告げたのに1週間生き延びた患者さんもありました。家族も遠くから帰ってきている時に限って、死はやってきません。気まずい空気が流れることもあります。
「死に目に会えますか?」と聞かれると「会えなくてもこうして会っていただいたことでよしとしましょう」と言ったりします。
死に目に会うって、ほんと難しい。何日も病室で寝ずの看病をしていた家族が、ちょっとコンビニに行った時に呼吸が止まるとか、家族がツルッと昼寝した時に止まっていたりします。でも、最後の最後の呼吸をもし見ることができたなら、心を通わせる人たちは大切な何かが腑に落ちるのを体験します。またすぐに忘れてしまうのですが、「明日はわが身」と自ずと気付きます。「先に逝って、待っててよ」と耳元で言う夫婦(めおと)、親子もあります。それはそれで有り難いこと。
このごろは、下顎呼吸の微細な変化を見抜き、家族を呼ぶタイミングを看護師と推し測ろうとしています。死に目にこだわる必要はないのですが、臨床にいると、死に目もいいもの持ってるわ、と童帰りをしているのか思ったりします。




































