
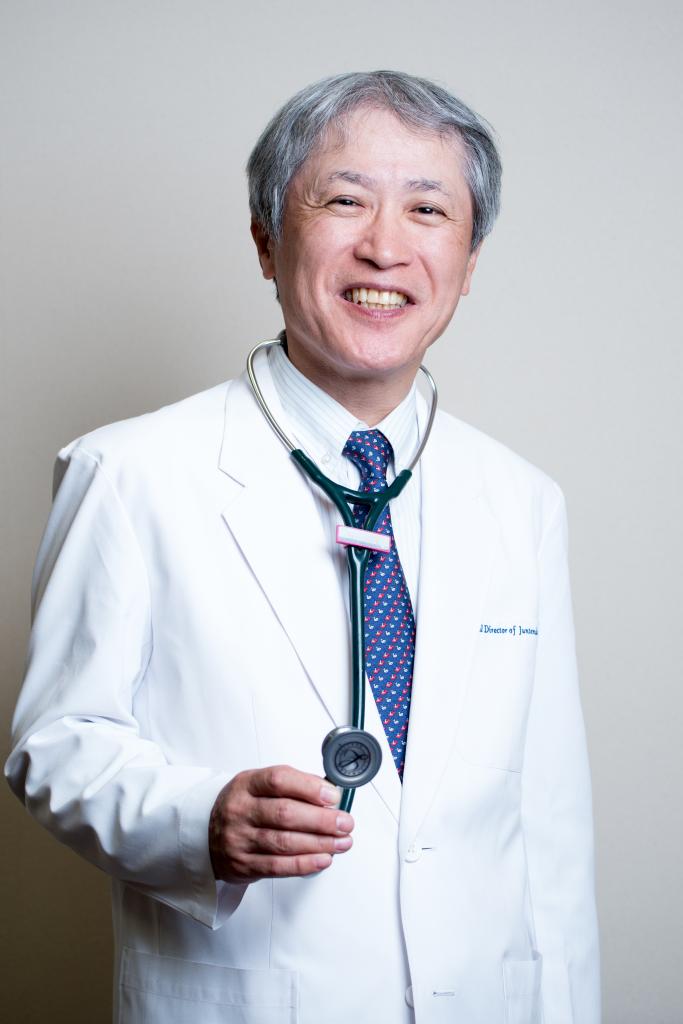
圧倒的な手術数と確かな技術で、心臓外科医の頂点に上り詰めた天野篤さんが、作家・林真理子さんとの対談にご登場です。平成の終わりが近づく今、現在の医療と世の中をどう見ているのか、マリコさんが迫ります。
* * *
林:そのうちAIが医療の分野にも進出してきて、医者の仕事もなくなってくるんじゃないかと言われてますけど、「冗談じゃない」と思ってらっしゃいますか。
天野:いや、患者さん向けの仕事は、医療従事者はしやすくなると思いますよ。たとえば調剤とか、その人に最適な検査とか治療のプロセスとかは、診断を入れたら今のワトソン(IBMのAI)クラスでもパパパッと答えを出してくれますからね。たとえば、同じ80歳の人でも、100歳まで生きたいと希望して、そのための治療を望むときに、「イチかバチかでもいいから100歳まで生きられる方法をとってくれ」という人もいれば、80歳で治療したら10年以上生きられるのに、「もう俺はいい。十分生きた。何もしないでくれ」という人も、いろんな人がいる。そういう大きな羅針盤の中のどれを選択するか。「もう生きたくない」という人を生きるほうに向けることがはたしていいのかどうか。そういう葛藤も含めて、いろんなデータをコンピューターに入れると、AIが「そういう患者さんならこういう方針をとったらどうか」と提案してくれるんだとしたら、われわれはラクですよね。
林:それはそうかもしれない。
天野:今、そのちょっと手前まで来てるんです。エビデンス・ベースト・メディシン(科学的根拠に基づく医療)になって、個々の患者さんを治療すると、その治療のリスクがどのぐらいあるかというのが出てきます。それをニューロコンピューター(人間の脳の機能を取り入れたコンピューター)に打ち込めば、そこから推薦される治療法が導き出せるはずなんです。
林:そうは言っても、患者さんに寄り添って力を導き出してあげるのは、やっぱり人間ですよね。
天野:もちろんそうです。今、自動車もオートマチック化して、高次な制御機能が入っていますけど、そういう中で古い自動車が軽んじられるかというと、一つひとつ手づくりでつくられたメカニカルな部分を好む人もいるじゃないですか。そういう部分が外科医の中では競争力として一部残るところがあって、絶対に必要な部分なんです。
林:私の感想ですけど、このごろ新聞の死亡欄を見ても、心臓が悪くて亡くなった人をあまり目にしないような気がするんです。





































