![[右]小林照子(こばやし・てるこ)/1935年生まれ、美容研究家。化粧品会社で美容を研究し「ナチュラルメイク」を創出。91年にコーセー取締役・総合美容研究所所長を退任後、56歳で「美・ファイン研究所」を設立。59歳で「フロムハンド小林照子メイクアップアカデミー」開校、83歳の今も「医療と美容の関係」に注目した活動実施 [左]小島貴子(こじま・たかこ)/1958年生まれ、東洋大学理工学部生体医工学科准教授、キャリアカウンセラー。埼玉県庁職業訓練指導員、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任准教授などを経て現職。著書多数 (撮影/写真部・片山菜緒子)](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/f/9/723mw/img_f9f58e674341eec7e36e96224c9bedc6115549.jpg)
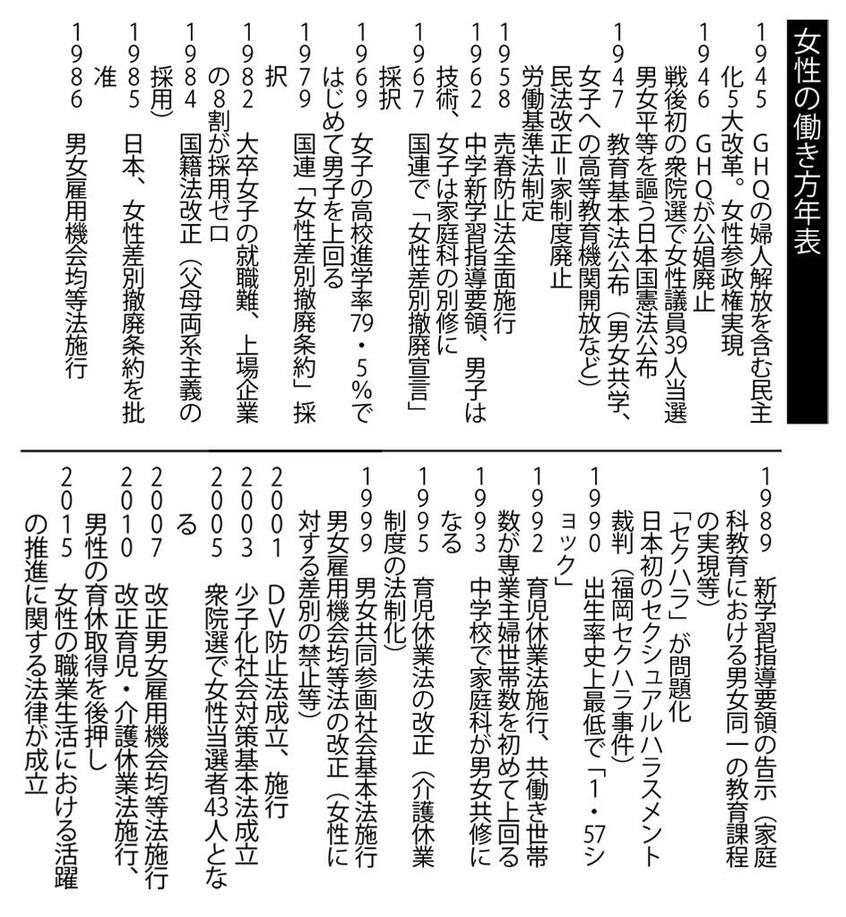
1986年、男女雇用機会均等法が施行された日本。当時、大卒で入社した女性たちが5年後、定年を迎えようとしている。人生100年時代、定年後を「余生」と呼ぶには長すぎる。「余生」ではなく「未来」にするために、何が必要か。コーセーで女性取締役としても活躍した美容研究家の小林照子さんは化粧品販売ではなくメイクやマッサージをひたすらしたと明かす。いったいなぜ? キャリアカウンセラーの小島貴子さんがその極意を聞いた。
* * *
小島:小林さんが歩んできた道も発想もオリジナリティーに溢れています。なぜ人と違うことができたのでしょう。
小林:現状を見た時に「なにか違うな」という気づきがあったから自分の道を見つけられたのかもしれませんね。私はメイクアップアーティストになりたくて、昭和30年に山形から東京に戻って美容学校に入学したんです。当時の日本の美容界には、伝統文化を頑なに守ろうとする美容家と西洋文化を良しとする美容家の2種類がいましたが、日本の現状を見て未来をつくっていこうという美容家はいなかった。ならば私がやろう、腕を上げようと思いました。
小島:コーセーに入社してからはいかがでしたか。
小林:コーセーで与えられたのは、「現場で化粧品を販売しなさい」という仕事でした。でも私は化粧品を売りもしないで、ただひたすらお客様にメイクやマッサージをしただけ。きれいになったお客様は大喜びで、私がメイクの時に使った化粧品を買ってくれる。結果的に化粧品は売れましたが、私自身が直接化粧品を売ったわけではないから、会社の方針には従っていないですよね。でも会社は実績(売り上げ)を見て「新人がよく売っているな」と評価してくれた。やはり結果を出すって大事なの。でも結果を出すまでの「手段」は私の自由。自由にやっていても売り上げという結果を出せたから「あいつはなにをやっているんだ!」とはならなかった。会社員時代はその繰り返しだった気がします。
小島:小林さんは温かく包み込むような話し方をします。地位や権力をもった女性の中には威圧的な物言いをする方も少なくありません。上に行った女性が、あとに続こうとしている女性に優しくできないと女性活躍は実現できないように思います。
小林:ああはなりたくないという悪い例になりますよね。そういう女性は往々にして「部下がついてこない」とぼやくけど、部下にしてみれば「いや、ついていきたくないよ」と思うような変な威厳が身についているんですよね。いつも人を言い負かしてしまう人がいますが、人とのコミュニケーションが下手なのね。
小島:コーセーで役員までつとめて独立。キャリア形成において、男性は一直線に上がっていこうとしますが、女性は停滞したり落ちたり紆余曲折しながらキャリアを重ねていく方が多いように思います。コーセーで役員に就任したら次は外資系企業に移るとか、ヘッドハンティングされるというのが男性的な生き方ですが、そうはしなかった。
小林:そもそも会社で役員になること自体が私の夢ではなくて、夢は別にありましたから。若い頃は自分が成長するために、一生懸命やりました。でもそれは会社のためというより「自分」のためだったのよ。会社には自由な人間がいる一方、命令に縛られたいタイプもいるわけ。私は自由にやっているほうでしたが、30歳の時に交通事故に巻き込まれたことで考え方が変わりました。香港に出張するため夫の運転する車で羽田空港に向かっていた道中、トラックがぶつかってきたんですね。自家用車は半分潰れ、夫は肋骨を5本折って肺に突き刺さるほどの大けが。私も全治3週間の打撲でした。不運な出来事でしたが、実は悪いことばかりではなかった。当時、私は自分の仕事と、事業を始めたばかりの夫のサポート、0歳の娘の育児もあってかなり無理をしていたんです。気づかないうちに肺浸潤(肺結核の初期)になっていましたし、その状態に歯止めをかけてくれたのが、この事故。私も夫も人生をリセットする冷静な時間を持つことができました。
小島:どのようにリセットを?
小林:家事で手を抜ける部分は抜いて、仕事に全力投球する生活に切り替えました。中途半端に頑張ることをやめたの。それから自分のためだけでなく会社のために頑張ろうと思えたのも、この時からです。けがをした私や家族のことを、同僚や先輩後輩が本当に心配してくれて、「ああ、温かいな」って感じたんです。「会社に貢献しよう」と素直に思いました。その後、ヒット商品を世に出して、会社に貢献できた。「会社のために頑張った!」と実感した時に、社会でもっと役に立てるかもしれないと思って独立を決めたんです。だから「自分」「会社」「社会」の順なんですよ、私の生き方は。
小島:退職後に幅広く社会活動をし、75歳の時には高校卒業資格が取得できる学校(青山ビューティ学院高等部)を設立しました。
小林:退職後は自分の使命として、ビジネス、ボランティア、後進の教育に取り組んできました。幅広い年齢層の役に立てるように活動してきたつもりでしたが、「思春期」の子どもたちを取り残していたことに気がつきました。思春期は、私も美容の道に進みたいという夢を持つようになった時。現代の子どもたちも「美」と関わりがある。スカートが短すぎるとか、こんな化粧はみっともないとか。大人に美意識を否定されて非行に走ったり引きこもったりして社会問題にもなっています。美意識が高いからこじれているので、そこを上手に支えればうまく乗り越えるのではないかと思いました。例えば、つけまつげをしたい、きれいにしたい、そういう思春期の子どもたちを「いいじゃない」と肯定しながら、教育をして社会に送り出しています。高卒の資格がないと、希望する仕事に就くことが難しいという現実も見てきていますから。
小島:すごい決断力です。60歳、70歳、80歳……と、今までの社会なら老後や余生と言われた年齢からいろいろなことをしていますよね。
小林:経験を重ねた75歳がやることには、誰も反対しません。年をとるほど耳の痛いことを言ってくれる人は減ってきますから、身近な人が指摘してくることは「真剣に考えてくれているからこそ」と素直に受け取るようにします。最近も「年だから体が心配」という理由で反対されたことはある(笑)。私がすべて見届けようと思っているわけではなく、次の人を育ててバトンタッチすることも同時並行でやっています。
小島:この世界でリーダーになれたのは、突き抜けた観察力と自分を客観視できる力のせいかもしれません。
小林:私が自分という世界をつくれたのは、同じことを誰もやっていなかったから。正確に言うと「誰もやっていないだろうと信じているから」です。実はもっとすごい人がいるかもしれないけれど、人のことは気にならないし比べようとも思いません。学校を創設した時も他の学校を参考にしたわけではなく、人を育てようと思ったら学校という仕組みになっただけ。比べる性格だったら「もっといい学校がいっぱいある」って、焦っていたかもしれないわね。
小島:先ほども仰っていましたが、著書の中で、自分は「家事」をしないほうに入れていますよね。
小林:もちろん家事が好きでやりたい人はやればいいのよ。でも「しなくちゃいけない」と、繰り返しながら人生を送るのはもったいない。私、「嫌ならしなくていいのよ」って囁いちゃう。その道のプロがいるんだから、プロを活用するのは大賛成。料理を重荷に感じる時は、無理せずプロの料理をいただけばいい。こんな味付けがあるのね、きれいな盛り付けだわ、このお皿はどこのかしら、などと美意識を養う機会にもなります。自分で作りたい日は作ればいいし。生活にメリハリをつけるのも、人生の楽しみ方の一つですよ。
(構成/ライター・熊谷わこ)
※週刊朝日 2019年1月4日号‐11日合併号






































