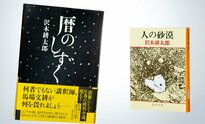別居してすでに15年。有賀さんは離婚を決意しているという。今は実母が晩年住んだ築46年の3DKの団地に一人で住み、年金(約12万円)を生活費に回し、団地のパトロールを月約1万円でするほか小学生が横断歩道を渡るのを見守る交通整理のバイト代(1万3千円程度)を演劇の月謝に充てている。退職金の数千万円は通帳ごと妻に持っていかれており、今後の生活は不安だ。独り身のせつなさが押し寄せ、団欒(だんらん)を思い出す正月がつらいという。
そんな有賀さんを、かんじゅく座を主宰する鯨エマさんはずっと見てきた。
「ご家庭のことでショゲて心身が老け込んでいらして。でも稽古を積んで舞台に立つうちに、表情が明るくなってきました」
内閣府の調べによると、65歳以上の一人暮らしの数は2010年に男性139万人、女性341万人。30年前に比べ、男性が約7倍、女性は約5倍に増えた。有賀さんのように、高齢になると離別したり、死別したりする人が多くなるからだ。
高齢者の環境が変わると痛手が大きい。精神科医の和田秀樹さんは言う。
「若いときと違い、年をとると心と体の結びつきが強くなる。落ち込んで食欲がないといって食べないと体力が落ち、風邪やインフルエンザにかかりやすくなる。免疫力が下がればそれがまた精神状態を悪くして、うつ状態から数年後にがんになることもあります」
和田医師が教えてくれた海外の研究(シドニー・ジスーク教授)でも、夫と死別したときにうつ病になった人は、ならなかった人に比べて免疫防御に関わるNK細胞の活性が低かった。妻に先立たれた男性の死亡率は、夫婦で暮らす男性の3~4倍という報告もある。
和田医師によれば、妻が専業主婦だった場合は、家事などをすべてする心理的な「お母さん」になっているので、男性は「伴侶」と「母親」の両方を失うことになり打撃が大きいのだという。共稼ぎの場合は、家事を分担しているケースも多いので妻への過度な依存はないが、愛情の深さは悲しみの深さに比例するという。
※週刊朝日 2015年12月25日号より抜粋