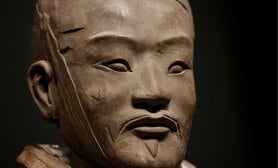ジャーナリストの田原総一朗氏は、アメリカにゆだねられてきた安全保障について時間をかけてきちんと議論すべきだという。
* * *
安保関連法案について、自民党の佐藤正久氏、民主党の福山哲郎氏、維新の党の小野次郎氏(いずれも参院議員)の3人に私が司会を務める「激論!クロスファイア」(BS朝日)に出演してもらい討論した。
そして、あらためて納得した。いわゆる集団的自衛権を日本の自衛隊が行使する機会はない。
自民党は公明党と閣議決定をして、「新3要件」を定めた。日本と親しい国、たとえばアメリカが他国から攻撃され、そのことによって日本の存立が根底から脅かされる危険性が明白な場合に、集団的自衛権を行使するというのである。
だが、第2次世界大戦後の70年間、アメリカが他国から攻撃されたことは一度もない。ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争など戦争は何度も行っているが、いずれもアメリカが仕掛けた戦争であり、先に攻撃されたケースはない。これからもアメリカが戦争を行うことはあるかもしれないが、それはアメリカが仕掛けるというパターンであろう。そして、アメリカが仕掛ける戦争は、「新3要件」に該当しないはずである。
ということは、安保関連法が成立しても、日本の自衛隊が戦争にかかわる可能性はないといえるのか。
「重要影響事態」では、日本は後方支援をすることになっている。かつてのベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争のようなことが今後起きた場合、アメリカから後方支援を要請されたら断れないのではないだろうか。
国会での審議を見ていると、政府は武力行使ではなく後方支援なので安全性が高い、リスクがほとんどないという答弁をしている。だが、政府側はわかってはいるのだろうが、この答弁は正しくない。戦う相手側にしてみれば、前方も後方もない。攻撃しやすいところを攻撃する。後方支援も危険なのである。
それに政府は、現に戦闘が行われていないところで後方支援活動を行い、戦闘状態になれば、作業を中止して撤退する、いわば逃げることになっているので危険性はないと説明している。だが、実際に戦闘状態になったからといって、撤退などできるのだろうか。後方支援とはいっても、アメリカ軍と共同作業をしているのであって、戦闘状態になったから撤退するのは裏切り行為になるのではないか。いや、それ以前に、何人もの自衛隊員に確かめたのだが、現実に戦闘状態になって撤退などできないということであった。
ところで、番組で3人の議論はほとんど進展しなかった。与野党が同じ「安全」「危険」という言葉を使っても、その意味が違いすぎるのである。議論を聞きながら、あらためて私たち日本人は戦後70年間、本気で具体的に安全保障について、それに戦争について、ほとんど議論してこなかったことを思い知らされた。安全保障は、言ってみればアメリカにゆだねてきたのである。
戦争について論及しないのが平和主義と考えてきたのを、今はじめて議論せざるをえなくなったから、与野党の議論がまったくかみ合わない。政府は法案を早く通そうなどとは思わず、何カ月も時間をかけるべきである。
※週刊朝日 2015年9月11日号