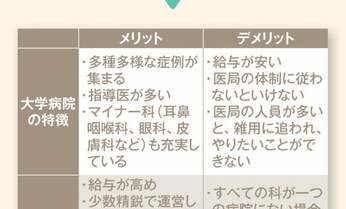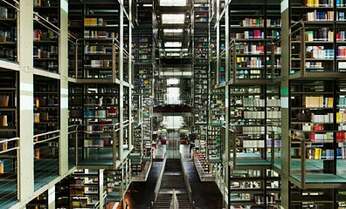「朝日新聞出版の本」に関する記事一覧


![[イベント] 東京の秋葉原で山岸伸氏 『北海道遺産 ばんえい競馬』 発売記念イベントが実施予定](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/b/0/346m/img_b05ad500b8ffe7d1590f621e332e53a224550.jpg)



シニア左翼とは何か
シニア左翼とは聞き慣れない言葉である。だけど、実態としては「はいはい」と思った人が多いのではないか。2015年の反安保法制デモで注目を集めたのはSEALDsなどの学生だったが、数として多かったのは圧倒的に中高年だった! 小林哲夫『シニア左翼とは何か』は3.11後、急に目立つようになったそんな60歳以上の左翼(広い意味での反体制運動の担い手たち)にスポットを当てた本である。 著者はまず、シニア左翼を四つのタイプに分ける。若い頃から活動を続けてきた「一貫組」。就職後は政治から遠ざかっていたが、定年をすぎて活動を再開した「復活組」(学者などに多い)。反体制的な意見を述べる文化人などの「『ご意見番』組」。どちらかといえば保守思想の持ち主だったが、60歳をすぎてはじめて運動に加わった「初参加組」。 〈いやあ、71年の『渋谷暴動』以来かなあ〉〈そうかあ、おれは『連赤』の年まではやっていた〉〈『サンイチイチ』で、おれは長い眠りから覚めた。復活したよ〉なんて同窓会みたいなやりとりに苦笑するけど、本人たちは楽しそう。 75歳以上の60年安保世代と65歳以上の69年全共闘世代が中心のせいか〈すべてのタイプに共通しているのが、「いずれにしても、残りの人生をかけて運動を行いたい」とする熱血派が多いことだ〉。 いってること、間違ってはいませんよ。先の戦争の退役軍人と元学生運動活動家を比べ〈歴戦の数々を語るメンタリティには通底するものがある〉という説にも、シニア左翼の活動は〈「終活」に向けた「リア充」の1つなのかも〉という意見にも笑った。でも、なんだろうね、真正面から批判するでも共感するでもない、採集してきた虫や植物を分類して標本箱に並べるような、この手つきは。 ちなみに著者は1960年生まれ。その昔、しらけ世代と呼ばれた世代だ。どこまでもシニカルな永遠の部外者。熱すぎるのもナンだけど、こっちはこっちでちょっとムカつく。
特集special feature


うめ婆行状記
昨年11月に66歳で逝去するまで、江戸時代の人情ものを書き続けた作家の遺作。亡くなる直前まで執筆し、小説は朝日新聞に連載された。 4人の子どもを育て終え、夫を亡くしたうめは五十路を前に独り暮らしを始める。思うままに生きてみたかった。大店の一人娘として育ち、町方の役人の家に嫁いだが武家のしきたりに馴染めずにきたのだ。30年仕えた夫は気が短く、義妹に貸した花嫁衣装やよそゆきの着物は戻らなかった。新居は、一緒になるためにひと肌脱いでやった弟の奥さんが見つけてきた。 面倒見のいいうめ婆の周囲には自然と人が集まる。30歳を過ぎても所帯を持っていなかった甥に頼られ、その甥が余所につくっていた子どもに慕われ、物語は歌舞伎の世話ものさながらに、笑いあり涙ありの展開を見せる。そして独り暮らしを決めたいきさつを周りから問われ、読者が想像し得なかったどんでん返しが語られるのだ。彼女の行く先には不安もある。だが、時代のふところの深さに包まれ、なんとかやっていけそうな著者の目配りが利いている。