
「読書」に関する記事一覧

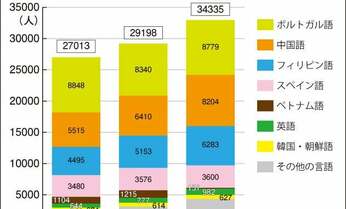




特集special feature






漢字で東大に合格!? 東大推薦入試合格者に聞いた面接一部始終
東大推薦入試は、2015年に始まった。募集人数は全学部合計で100名程度。倍率は、平成31年度で2.8倍程度と決して高くないが、じつは狭き門である。これまで4度行われた東大の推薦入試において、合格者数は100名に達したことはない。初年度の合格者が77名ともっとも多く、今春の合格者は定員に大きく及ばずわずか61名だった。推薦入試は、東大で学び、研究するのにふさわしい学生を厳選するための試験であることが読み取れる。東大生の中でも選ばれた存在であるともいえる推薦入学者。クイズ本『東大 漢トレ』(朝日新聞出版)の著者である間辺美樹さんも、その一人だ。平成30年度の工学部推薦入試に合格した間辺さんは、「漢字」で東大合格を勝ち取ったという。知られざる推薦入試の実態について間辺さんに話を聞いた。

































