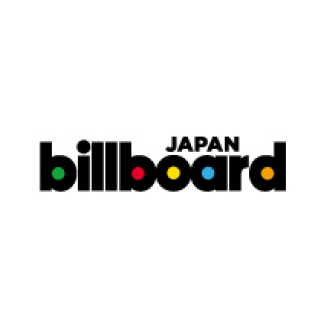昨年11月に東京キネマ倶楽部で開催されたTele初のワンマンライブ【東京宣言】から約3か月半、2度目のワンマンとして行われた東京・大阪でのライブ【nai ma ze】。以下はその東京編、2月19日・Spotify O-EASTでのライブのレポートである。進化とか成長とか、そういう言葉では説明が追いつかない、Teleというアーティストとオーディエンスの関係性が根本からガラリと変わったのだということを証明するライブだった。前回のほぼ倍、大きく会場の規模を拡大して繰り広げられた一夜、ステージから放たれるTeleの音楽と言葉とパフォーマンスはとても大きくてフレンドリーだった。
ライブは「ロックスター」と「東京宣言」、つまり前回の【東京宣言】の時点でTeleの現在地を示す最新曲として披露された2曲からスタートした。この【nai ma ze】は【東京宣言】のその先で始まるのだ、というメッセージだ。実際、この日演奏された曲のほとんどはキネマ倶楽部でも演奏された曲たちだが、その響き方、届き方には明らかな違いがあった。いわば「挑戦者」としての姿勢がある種の鋭さを生んでいたあの日に対して、この日のTeleの音楽は、同じ場所に集まった人々と分かち合われるために鳴っている、そんな感じがライブ全体を通してあった。
「誰も愛せない人」をオーディエンスの手拍子とともに軽快に鳴らすと、続く「アンダルシア」のメロディが空を突き抜けるように広がる。バンドのメンバーとの呼吸もぴったりで、力強いサウンドを背に喜多朗の歌も曲を重ねるごとにどんどん強く、大きくなっていく。しかしその強さは観客の喉元にナイフを突きつけるようなものではない。おおらかな優しさをもって包み込むような強さだ。「どうやら皆さん、ようやく声を出していいようですよ。今日から僕のライブではお行儀のいい人はいらない、そういうことでしょ?」。ここから新たな関係を作ろう、と呼びかけるような喜多朗の言葉にフロアは歓声で応える。そして披露されたのは「Veranda」。ドラムとギターが刻むリズムに合わせて、オーディエンスからは自然発生的に手拍子が起きる。その真ん中にいる喜多朗も笑顔を見せながら、そんな会場の空気を楽しんでいるようだ。
新型コロナウィルスの感染拡大下において観客に課せられていた制限も、ここにきてようやく解消されつつある。マスク越しではあっても、声を出して歌ったり声援を送ったりすることができるようになった。実際にこの日も曲間にエールのような声が飛んだり、喜多朗がMCで話す言葉に笑い声が起きたりしていた。そういう状況の変化もあって、とにかくこの日の喜多朗はコミュニケーションを求めていた。隙あらばオーディエンスを煽り、率先して手を叩き、激しいアクションを交えながら一緒にライブを作ろうと訴えていた。力強いテンポでぐんぐんと前身するような「私小説」でも喜多朗はフロアに呼びかける。「今、ここで全員が跳べるかって聞いてんの!」。その言葉に呼応して飛び跳ねるオーディエンス。この何年かで溜まってきたものを振り払うように、高いテンションでライブは続いていく。
「3年弱、僕たちを縛った呪いみたいなものは一朝一夕では解けないから。今日は無理矢理みなさんの呪いを剥がしにやってきました、Teleです」。そんな言葉とともに披露されたのは「花筏」と題された新曲。現時点でリリースは未定だが、とても純粋で肯定的な思いに貫かれた、美しいバラードだと感じた。いつ書かれた曲なのかとか、どんな思いを込めた曲なのかとか、まったく知らないで書くのだが、この曲のすべて丸ごと抱き締めるような大きさは、確かにこの日のライブでTeleが見せたものと直結しているように思えた。そんな「花筏」から一転して「バースデイ」へ。森夏彦のベースが印象的なリフを弾き、ギターが後に続く。ズンズンとパワフルなリズムとともに喜多朗は声を張り上げ、「もっともっと!」とフロアを煽り立て、大音量の手拍子を呼び起こしていく。歌い終えるとバンドを残してステージを去っていく喜多朗。なんだなんだと思っているうちに曲が終わり、今度はバンドメンバーがいなくなって喜多朗ひとりが戻ってきた。
アコギをぶら下げ、「このステージを端から端まで歩いたら13歩くらいだったんですよ。覚えておこうと思って」と語り始める喜多朗。「たぶんこれからもっと大きいところでやるだろうし、もっとたくさんの人たちの前でやるんだけど、第2回目のワンマンのステージは13歩。これが100歩、1000歩、10000歩になったときには、僕の脚だけじゃきっと足りないから。今ここに集まってくれたみなさんの歩幅も一緒に足していきたいなと思ったんです」。自分で言っておいて「何言ってるかわからないでしょ?」と笑っていた喜多朗だが、その独特の表現に込めた気持ちはきっと愛の告白のようなもので、その告白は間違いなく観客ひとりひとりに届いていたと思う。そして弾き語りで「クレイ」を披露すると、再びバンドメンバーが帰ってきて始まったのは2月15日にリリースされた最新デジタルシングルの「鯨の子」だ。ゆったりとしたグルーヴは音源で聴く以上に温かさを感じさせる。喜多朗はステージの端から端まで歩きつつオーディエンスに「みんなの声を聞かせて」と語りかけ、自ら率先するように力いっぱいに歌い上げた。
華やかな祝祭感が広がった「comedy」で、この日一番の一体感がO-EASTに生まれる。先ほどのMCから「クレイ」、そして「鯨の子」の流れの中で、ステージ上とステージの下を区切る境界線が少しだけ緩んだようだ。とてもオーガニックなコミュニケーションがTeleとオーディエンスの間に生まれ始めている。そのままひと繋ぎで披露されたのが「ghost」。ポツリポツリと独白するようなこの曲が、「comedy」で解れた心に染み入ってくるような感覚になる。ファーストアルバムのラストに収められていたこの曲ももちろん、前回のワンマンライブで披露されていた曲だ。だがその響きは、そして場に生まれる空気は、あのときとははっきりと違って、とても強く、凛としていた。
その「ghost」で本編を締めくくり、ステージを去っていった喜多朗とバンドメンバー。しかしフロアから放たれる「アンコール」の声と手拍子が彼らを呼び戻す。再登場するや否や「これは説教だね」とフロアに告げる喜多朗。「声の出し方のフォームがまだできてないね。一緒にやっていきましょう」。そして「花瓶」を歌い始める。するとどうだろう、フロアから自然と大合唱が巻き起こっていく。今日のライブの最初から、あるいはそれよりもずっと前から撒き続けてきた種が芽吹いたような、鮮やかな感動が襲ってくる。喜多朗がステージから語りかけてきた言葉、パフォーマンスで示してきた態度、すべてが結実したようなシンガロングは、曲の最後まで鳴り止むことはなかった。これなのだ。Teleという存在をプレゼンテーションするだけではない、コミュニケーションの場としてライブを成立させること。それが彼の語った「歩幅を一緒に足していく」ということだとすれば、早くも彼はこのアンコールでその景色を現実のものにしてみせたことになる。
「まだ声を出せない、出しちゃいけないっていう時期に活動を始めて。最悪なことばっかりの中で唯一よかったなって思えるのは、緊張感からの解放みたいなものを、僕のことを好きでいてくれる人たちと一緒に味わえたということ。それだけでも、僕は2021年から音楽を始めてよかったなって思います」。「花瓶」での大合唱を受けて喜多朗が語った言葉は、掛け値のない実感だったはずだ。最後に披露された「生活の折に」はまだTeleがバンドだった時代に彼が作った曲。不思議なことにその曲は、今こうしてひとりで生み出している曲たちよりもよっぽど孤独に聞こえる。その「原点」を忘れることなく、今日手にした喜びも解放感も携えて進んでいく。そんな宣言を聞いているような気分で、Tele2度目のワンマンライブは終わりを迎えたのだった。
Text:小川智宏
Photo:山川哲矢
◎公演情報
【nai ma ze】
2023年2月19日(日)
東京・渋谷Spotify O-EAST
◎ツアー情報
【Tele TOUR 2023「祝 / 呪」】
2023年09月28日(木)北海道・札幌PENNY LANE 24
2023年10月03日(火)愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2023年10月05日(木)宮城・仙台Rensa
2023年10月11日(水)福岡・BEAT STATION
2023年10月13日(金)大阪・なんばHatch
2023年10月05日(日)東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)