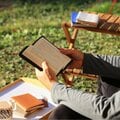三人は主役になれる技量も備えながらも、組織が機能するために自らをなげうって戦える。いち早くポジションの良い味方を見つけ出してボールを届け、プレー効率を高め、目立とうとしない。味方のパスコースを確保し、敵の行く手を遮る。あるいはチームが崩れ落ちそうになる気配を感じ取り、カバーするポジションを取って補強できる。敵に流れを与えず、堅実な仕事を繰り返せる。
明神、阿部、長谷部がチームの回路を支えたワールドカップやアジアカップは、安定した戦いで成功を収めている。
長谷部は自身が得点やアシストをたたき出さなくとも、適切な攻守の選択によって、周りの選手の力を10パーセントは引き上げられる。ハリルホジッチが率いる日本代表は今年に入って調子を落としているが、その理由が長谷部のケガによる離脱であることは明らかだろう。半歩の立ち方の違いで、チャンスとピンチの分かれ目になるのが、トッププロの世界だ。
そして、黒子はサイドやベンチやスタッフにも欠かせない。2002年の日韓ワールドカップを戦ったフィリップ・トルシエがベテランFW中山雅史をメンバーに入れたのは、そのキャラクターや経験によるものだった。2010年の南アフリカワールドカップでは、岡田武史監督が川口能活をチームの重しになれる存在として選出。そのどちらの大会もベスト16に進出している点は興味深い。
日本代表ではないが、鹿島が2007年からリーグ3連覇した最強時代、セカンドGKとしてチームを下支えした小澤英明のような黒子もいる。黙々と練習に励み、少しも倦まず、ベンチから味方に声援を送る。誰にでもできる献身ではない。
黒子は「チームを勝たせたい」という渇望を持っている必要がある。同時に「自分が活躍したい」という欲望も根底にあるが、それを隠せる。わが身を弁えながら、命を懸けるように戦いに挑める。
勝利する集団は、黒子なしでは語れない。
小宮良之
1972年生まれ。スポーツライター。01~06年までバルセロナを拠点に活動、帰国後は戦うアスリートの実像に迫る。代表作に「導かれし者」(角川文庫)、「アンチ・ドロップアウト」3部作(集英社)、「おれは最後に笑う」(東邦出版)など。3月下旬に「選ばれし者への挑戦状」(東邦出版)を刊行予定